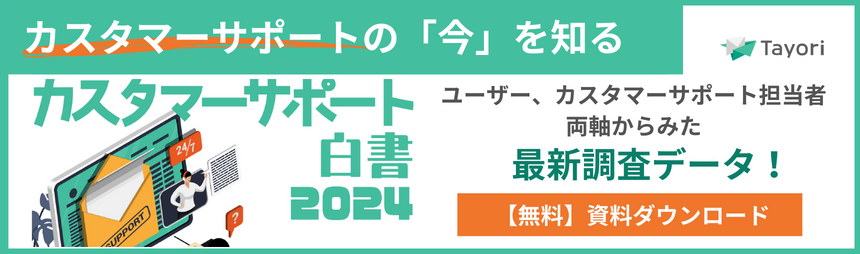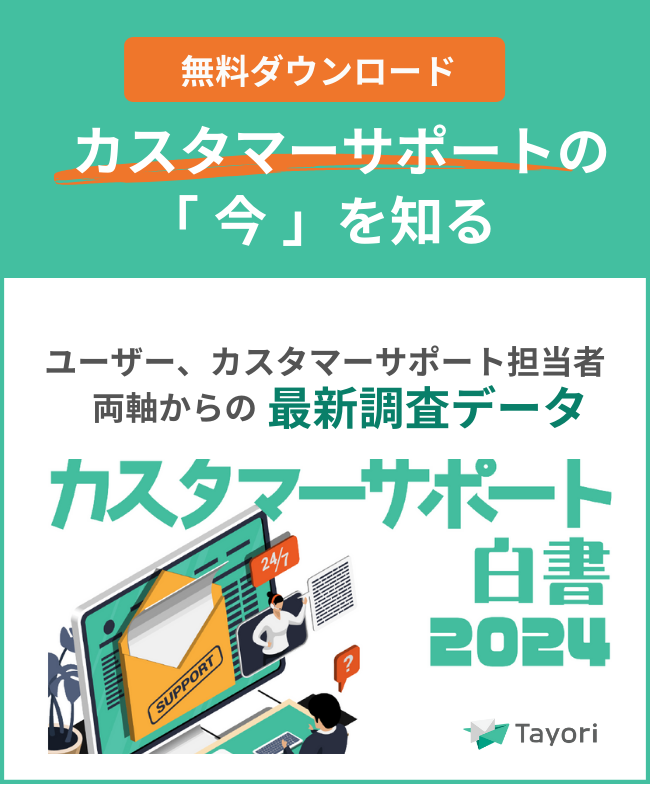心理的安全性とは?高めるための5つの施策・メリット・デメリット・注意点まで紹介

生産性の向上や働きやすい環境作りにも役立つ「心理的安全性」についてご存知でしょうか。
本記事では、心理的安全性が高いことによるメリット、低いことによるデメリットを解説。心理的安全性を高めるための、5つの施策も紹介します。
心理的安全性とは?
心理的安全性とは、周囲の反応に怯えることなく、安心して働ける状態を指す言葉です。
心理的安全性は、1999年にハーバード大学のエイミー・エドモンソン教授により提唱されました。さらに、2015年にGoogleが心理的安全性に関する発言をしたことで、多くの企業が関心を寄せるようになりました。
心理的安全性が注目されている背景
心理的安全性が注目されている背景には、Googleによる「心理的安全性は成功するチームの構築に最も重要なものである」という発言があります。
Googleは2012年から「プロジェクトアリストテレス」と呼ばれる、生産性向上プロジェクトに取り組んできました。約4年の歳月をかけ、さまざまなチームを分析した結果、Googleは「成功するチームは心理的安全性を確保している」という結論に至りました。
参考:The New York Times Magazine
心理的安全性の測定方法
心理的安全性を測定する方法には、「質問による測定」と「観察による測定」の2つの方法があります。
質問による測定では、チームメンバーに対して「心理的安全性を測る7つの質問」を投げかけ、質問への答えから心理的安全性を測定します。
心理的安全性の提唱者エドモンドソン教授によると、以下の7つの質問が有効的です。
- チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。
- チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
- チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。
- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。
引用:Google
観察による測定は、チームメンバーが職場でどのようなサインを出しているのかを観察する方法です。心理的安全性の高い職場では、「メンバーが仕事の失敗についても積極的に話をする」というような、一定のサインがあります。
観察するサインを決めて、観察を行うのも有効的な方法だといえるでしょう。
職場の心理的安全性が確保されていることの3つのメリット
職場の心理的安全性が確保されていることには、下記のような3つのメリットがあります。
【心理的安全性を確保する3つのメリット】
- ポテンシャルを最大限に発揮できるようになる
- 情報共有やアイデア・改善案の提案が活発になる
- 定着率が高まる
心理的安全性を確保することは、働きやすく、生産性の高い職場作りに繋がります。それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
1.ポテンシャルを最大限に発揮できるようになる
心理的安全性が確保されている職場は、常に最大限のポテンシャルを発揮できる職場です。
どんなに能力の高い人材でも、精神的に緊張していては、本来の能力は発揮できません。心理的安全性が確保され、常にリラックスして働ける職場では、いつでも最大限のポテンシャルを発揮できます。
2.情報共有やアイデア・改善案の提案が活発になる
心理的安全性を確保することで、情報共有やアイデア・改善案の提案が活発になります。
心理的安全性の低い職場では、「こんなことを言って、否定されたり馬鹿にされたりしないだろうか」という不安がつきまといます。心理的安全性を確保することで、周囲からの否定を恐れずに、活発な意見交換が可能になるのです。
3.定着率が高まる
心理的安全性の確保は、人材の定着率向上にも繋がります。
心理的安全性が高い職場では、誰もがリラックスしながら能力を発揮し、否定を恐れずに活発な意見交換を行います。言い換えれば、仕事にやりがいを感じられる居心地の良い職場であり、人材の定着率も自然と高まるのです。
職場の心理的安全性が低いことのデメリット
心理的安全性が低い職場のデメリットは、常に不安を感じながら働かなければならないことです。不安を感じながら働くことは、生産性の低下や離職率の増加に繋がります。
心理的安全性が確保されていないと、周囲からの否定を恐れて、本来必要な情報共有や意見交換が行われなくなります。職場にいること自体がストレスになり、緊張しながら働くことになるため、本来のポテンシャルも発揮できません。
ストレスに耐えかねたメンバーは、次々と仕事を辞めていくでしょう。
心理的安全性が低いことは、企業にとって大きな危機にも繋がりかねないといえます。
職場の心理的安全性を高める方法・施策を5つ紹介
では、職場の心理的安全性を高めていくためにはどうしたらいいのでしょうか。今回は、職場の心理的安全性を高める5つの方法・施策を紹介します。
【心理的安全性を高める5つの方法・施策】
- 多様性を認める
- 組織の透明性を上げる
- ピアラーニング・ピアボーナスを取り入れる
- 1on1や雑談で信頼関係を築く
- 安心感から無責任にならないような組織作りが重要
それぞれの具体的な方法や、施策ごとのメリットを詳しく確認していきましょう。
多様性を認める
心理的安全性を高める1つ目の方法は、「多様性を認める」ことです。
多様性が認められた職場では、発言することに対する不安がなくなります。「こんなことを言って、おかしく思われないだろうか」といった不安がなくなり、誰もが安心して発言できるようになるのです。
また、多様性を認めることは、メンバー同士が尊重しあう風土の形成にも役立ちます。
組織の透明性を上げる
心理的安全性を高める2つ目の方法は、「組織の透明性を上げる」ことです。
仕事内容や評価基準の透明性を上げることはもちろん、自分の出した意見がどのように扱われているのか、わかるようにする取り組みも効果的です。
評価基準の透明性を上げることは、「どうすれば出世できるのか」を明確にすることにも繋がり、メンバーのモチベーションアップにも役立ちます。
ピアラーニング・ピアボーナスを取り入れる
心理的安全性を高める3つ目の方法は、「ピアラーニング・ピアボーナスを取り入れる」ことです。
ピアラーニングとは、メンバーが互いに協力し合い、学び合う学習方法を指します。ピアボーナスは、メンバー同士が互いの仕事を認め合い賞賛し合いながら、具体的な報酬を贈り合う仕組みです。
チームメンバーが互いに認め合い、協力しながら、仕事やスキルアップができる環境をつくることが大切です。
1on1や雑談で信頼関係を築く
心理的安全性を高める4つ目の方法は、「1on1や雑談で信頼関係を築く」ことです。
1on1とは、名前の通り、1対1で行う面談のことです。周囲の目がない落ち着いた場所で、1対1で本音を話すことは、信頼関係の構築に役立ちます。
定期的な1on1が難しい場合は、積極的な雑談を取り入れることでカバーできます。要は、「本音で話せる」という信頼感を与えることが重要なのです。
安心感から無責任にならないような組織作りが重要
心理的安全性を高める5つ目の方法は、「安心感から無責任にならないような組織作りをする」ことです。
心理的安全性の高い職場は、誰もがリラックスした状態で、能力を発揮したり意見交換したりできる職場です。メンバー同士の仲が良いだけの職場や、ラクができる職場のことではありません。
1人1人の役割や上司と部下の関係性がハッキリした組織編成を行い、明確なビジョンをもって仕事に取り組めば、安心感と責任感が両立した組織作りができるでしょう。
心理的安全性を高めるためのルール作りを行おう
心理的安全性を高めるためには、ルール作りが必要です。
組織の透明性を上げ、定期的な1on1や雑談で本音を伝え合うことで、多様性を認める風土が自然とできあがっていくでしょう。ピアラーニング・ピアボーナスのような、メンバー同士の協力を促進するための仕組み作りも役立ちます。
心理的安全性を高めるためのルール作りだけでなく、ルールに基づいた運用がなされているか、定期的に確認することも大切です。心理的安全性の目的は、あくまで生産性の高いチーム作りです。ダラダラとした馴れ合いになってしまわないよう、上司や部下の関係性、1人1人の役割は明確にすべきです。
心理的安全性を高めるための取り組みをする際は、自社に合ったルールをよく考えましょう。心理的安全性を適切に活用すれば、Googleのような生産性の高い働き方も、夢ではありません。
ルールを一覧化し、管理する際には、株式会社PR TIMESが運営する「Tayori」を活用すると便利です。

導入事例:PR TIMES 当社テレワーク対応
Tayoriの「よくある質問(FAQ)」機能を使うことで、などのカテゴリ別にあわせた規則を分類可能。
タグを設定することも可能なので、従業員が「働き方」「出社規定」など特定の内容を確認したい場合、キーワードを入れて簡単に検索できます。
社内の心理的安全性を高めるルールを管理するためにも、従業員に周知させるためにも使えるTayori。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。