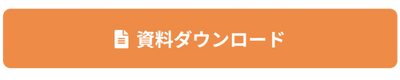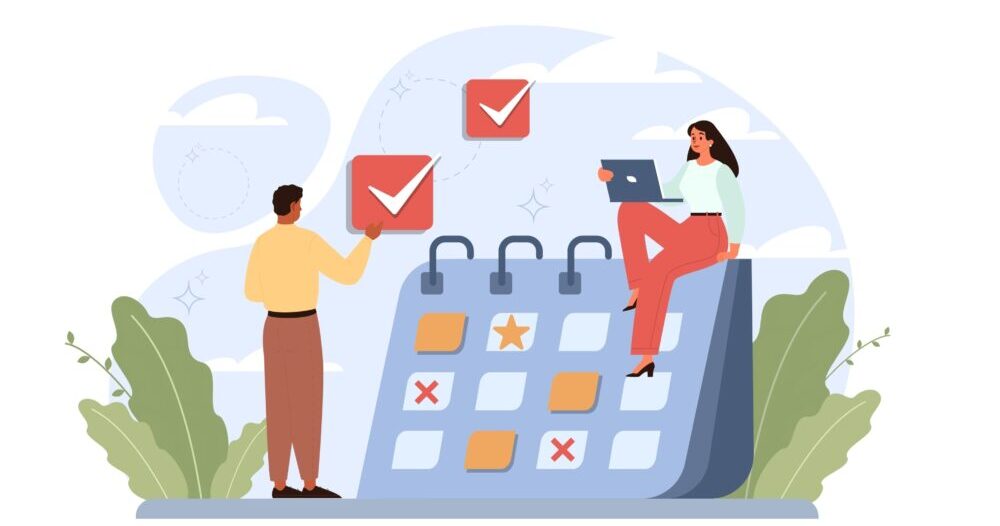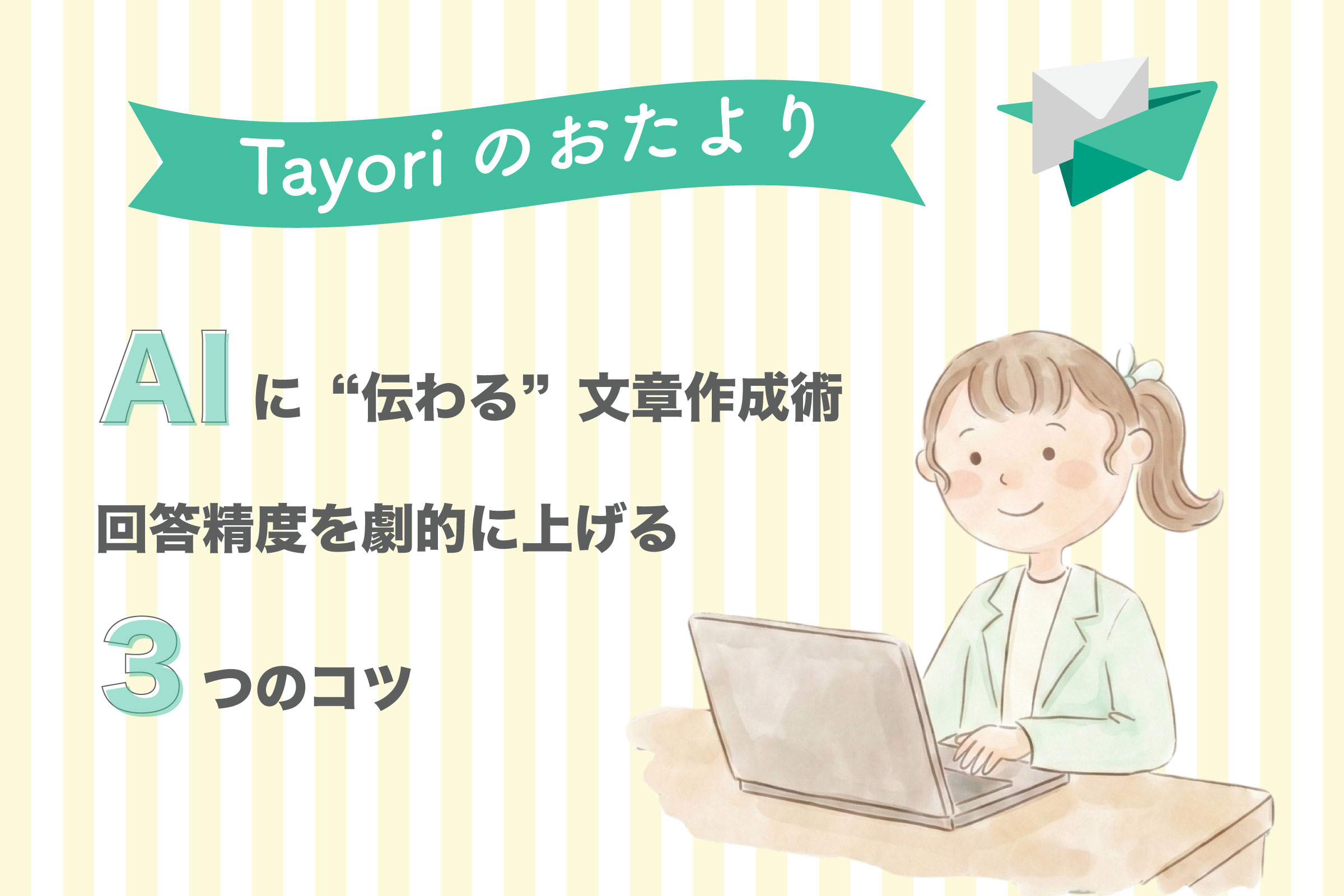サポートチケットとは?メリット・システムの仕組み・導入時の注意点を解説
 ユーザーがサポートを受けるために必要なチケットと引き換えにカスタマーサポートを受ける「サポートチケット」。導入するか検討している企業も多いのではないでしょうか。
ユーザーがサポートを受けるために必要なチケットと引き換えにカスタマーサポートを受ける「サポートチケット」。導入するか検討している企業も多いのではないでしょうか。
今回は、サポートチケットを導入するメリットから、注意点までを紹介します。サポートチケットに関する基礎知識を付けたい方は、ぜひご確認ください。
【目次】
- サポートチケットとは?
- サポートチケットを導入する企業側のメリット
- サポートチケットを導入する顧客側のメリット
- サポートチケットのシステム・仕組み
- サポートチケットを導入するときの注意点
- サポートチケットを導入する際には、事前準備が重要
サポートチケットとは?
カスタマーサポートへの問い合わせに、回数制限を付けている企業はほとんどなく、無条件で問い合わせの対応やサポートをしている企業が多いでしょう。
一方、サポートチケットとは、「チケット」と引き換えにサポートを提供するカスタマーサポートの仕組みです。
物理的なチケットがあるのではなく、Web上でチケットを消費します。
キャンペーンや初回利用時にはチケットが無償で配布されることもありますが、多くのケースでチケットは有料です。つまり、ユーザーは有償でサポートを受ける必要があることに従来のカスタマーサポートの違いがあるといえるでしょう。
サポートチケットを導入する企業側のメリット
従来のように無条件でサポートをするのではなく、チケットと引き換えに問い合わせ対応をすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。
企業側には主に以下の3つのメリットがあります。
- サポートの運営コストを削減できる
- カスタマーサポートの履歴を残せる
- 異なるチャネルからの問い合わせにも対応できる
それぞれの詳細を確認していきましょう。
サポートの運営コストを削減できる
無償で問い合わせができる場合、本来であれば自己解決できるような軽微な内容であっても、カスタマーサポートに問い合わせされるケースも多いもの。
カスタマーサポートは限られた人数、限られた時間で運営されています。本来であれば、サポートを必要としていない軽微なお問い合わせの対応に追われてしまうことでコストがかかっていることも多々あります。
チケット制にすることで、本当にサポートを必要としているユーザーからの問い合わせに集中することが可能になり、運営コストの削減に貢献します。
カスタマーサポートの対応を一元化し履歴を残せる
ユーザーとのタッチポイントは多様化しており、電話・お問い合わせフォーム・メール・チャット・SNSなど様々なチャネルで問い合わせ対応が発生しているケースもあります。1人のユーザーから別のチャネルで問い合わせがあった場合、過去の問い合わせ履歴を参照することが難しいケースも発生します。
チケット化することで、チケットの対応番号を元にカスタマーサポートの対応を一元化することが可能です。サポートの履歴を残せることで、異なるチャネルからの問い合わせへも一貫したサービスの提供が行えます。
商品やサービスの課題分析に有効
カスタマーサポートに寄せられる内容を一元管理できることで、商品やサービスの課題を分析する際にも役に立ちます。
例えば、トラブルAに関する問い合わせがあったチケットを確認することで、トラブルの範囲を把握できます。特定の範囲や条件で発生していることがわかると、エラーの改善を効率的に行うことが可能です。
また、ユーザーからの問い合わせ内容を分類することでニーズを把握し、サービスの改善に繋げることも期待できます。
このように、サポートチケットはサポートの運営コストを削減し、サポートの対応品質の向上させるだけでなく、サービス全体の品質向上にも繋がるといったメリットがあります。
サポートチケットを導入する顧客側のメリット

サポートチケットは企業にとっては多数のメリットがあることがわかりましたが、顧客にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
これまで無償でサポートを受けていた顧客からすると、サポートを有償で受ける必要があることに抵抗を感じる人もいるかもしれません。しかし、サポートチケットは顧客にとってもメリットが大きいものです。
次に、サポートチケットを導入する顧客のメリットである、以下の2点について紹介します。
- 必要なときに迅速なサポートを受けられる
- 高品質なサポートを受けられる
必要なときに迅速にサポートを受けられる
迅速に解決したいことがありカスタマーサポートに問い合わせをしても、電話が繋がらなかったり、メールの返信が返ってこなくてもどかしい思いをしたことがある人も多いでしょう。
サポートをチケット化することで、重要性の低い問い合わせが減り、カスタマーサポートへ繋がりやすくなります。
本当にサポートを必要としているときに、これまでよりも迅速にサポートが受けられるのは顧客にとってもストレスが少なく、大きなメリットだといえるのではないでしょうか。
高品質なサポートを受けられる
サポート対応を有償化することで、企業もより高品質なサポートを提供する体制を整えます。人材への教育やサポート内容を充実化させるに伴い、高品質なサポートを受けられる
カスタマーサポートへの問い合わせが減少することで、ひとつひとつの問い合わせにしっかりと向き合うことができるようになるため、より手厚いサポートが受けられるようになるのもメリットです。
サポートチケットのシステム・仕組み
企業だけでなく、顧客にもメリットが大きいサポートチケットは、どのようなシステムや仕組みで運用されるのでしょうか。
すでに紹介したように、サポートチケットはWeb上で管理されるデジタルチケットです。ユーザーがWeb上でチケットを購入し、問い合わせを行うごとにチケットが消費される仕組みです。
チケットにユーザーごとのIDを付与することで、異なるチャネルからの問い合わせであっても、過去の問い合わせ履歴を元に対応が可能となります。
サポートチケットを導入するときの注意点
ユーザーはこれまでの無償でのサポートに慣れているため、有償でのサービスを提供する際には、その制度を正しく理解してもらうことでトラブルを防ぎましょう。
サポートチケットの性質上、導入する際には以下の3点に注意をして仕組みを作ることが重要です。
- チケット1枚での対応範囲を明確にしておく
- チケットの有効期限を明確にしておく
- チケットを消費しなくても問題解決できる仕組みを整える
それぞれの詳細を詳しく解説します。
チケット1枚での対応範囲を明確にしておく
サポートチケットを販売する際には、対応範囲を明確にし、ユーザーに誤解を与えないようにすることが重要です。
一般的には、チケット1枚で1つのサポートやトラブルの解決を行います。1回の問い合わせで3つのサポートが必要になった場合は、チケットを3枚消費することになります。
サポート範囲やサポート内容を予め明確にしておくことで、トラブルを防ぎます。
また、「チケットを消費しないため、まとめて質問しよう」といったことが起きにくくなり、適切なタイミングでのサポートが可能になることもメリットです。
チケットの有効期限を明確にしておく
購入したチケットは、有効期限を明確にしておくことも大切です。
チケットを適量購入してもらえることで、サポートの業務量をある程度予測できるようになります。大量のチケットの購入は、サポートの業務量をコントロールしにくくなるだけでなく、サービス終了後に残っているチケットへの対応をめぐりトラブルに発展する可能性も考えられます。
購入から6ヶ月、1年など有効期限を設けておき、過ぎた場合は無効にするなど、購入前にユーザーに認識してもらうようにしてください。
チケットを消費しなくても問題解決できる仕組みを整える
サポートチケットの導入で、サポートを有償化する際には、簡単なトラブルなどは自己解決できる仕組みを作っておくことが欠かせません。
UIがわかりにくかった場合でも有償で質問をしないといけない場合、継続率や顧客満足度に影響するでしょう。
ユーザー自身で問題を解決するためには、オンラインコミュニティの構築や、よくある質問・FAQページの作成が効果的です。
FAQページは、以下の3つのポイントを押さえて作成することが効果的です。
- 探している情報がスピーディーに見つかる
- 知りたい情報や疑問が確実に解決する
- 簡潔に理解でき視覚的にもイメージできる
関連記事:わかりやすいFAQページ・サイトの特徴とは?構築するための10のポイントを解説
「質疑応答形式で記載する」「質問の粒度を揃える」「質問内容はユーザーの立場・目線から作成する」などのポイントを元に、ユーザーが使いやすいFAQを準備することがポイントです。
関連記事:満足度が上がるFAQの書き方10のTIPSとは?残念なFAQの特徴も合わせてチェック
関連記事:【先回りするカスタマーサポート】セルフサービスの体制を整える3つの方法
サポートチケットを導入する際には、事前準備が重要
サポートチケットの導入により、顧客に迅速かつ高品質なサポートを提供できるようになるだけではなく、企業もサポートの運営コストの削減や課題分析を効率的に行えるなど様々なメリットがあります。
まだ一般的に浸透しているとはいえないシステムのため、導入する際には、対応範囲や有効期限の明確化や、チケットを使用しなくても問題解決できる仕組みを作るなどの事前準備が欠かせません。
事前準備として必ず準備しておきたいものの一つが、FAQ(よくある質問)です。
カスタマーサポートツール「Tayori」を使うと、複雑な技術を使うことなく、機能性に優れたFAQを作成できます。

カテゴリごとに分類したり、タグを設定できたりなど検索性が高いマニュアルを作成できるため、ユーザーにとって使いやすい実用的なマニュアルを作れます。デザインの統一も簡単で、ブランディングを重視する企業にもおすすめです。
もちろん作成時には特別な技術は必要なく、直感的に操作できます。

パスワードやIP制限もできるので、特定のユーザーに向けた内容を掲載する際にも安心です。無料プランもあるので、ぜひ「Tayori」をマニュアルの作成・管理・運用に役立て、顧客が課題を自己解決できる仕組みを作ってみてはいかがでしょうか。