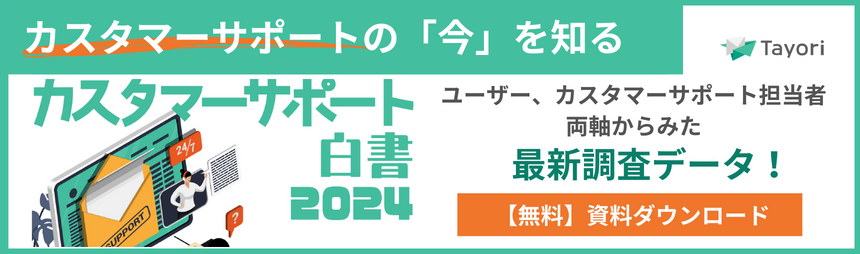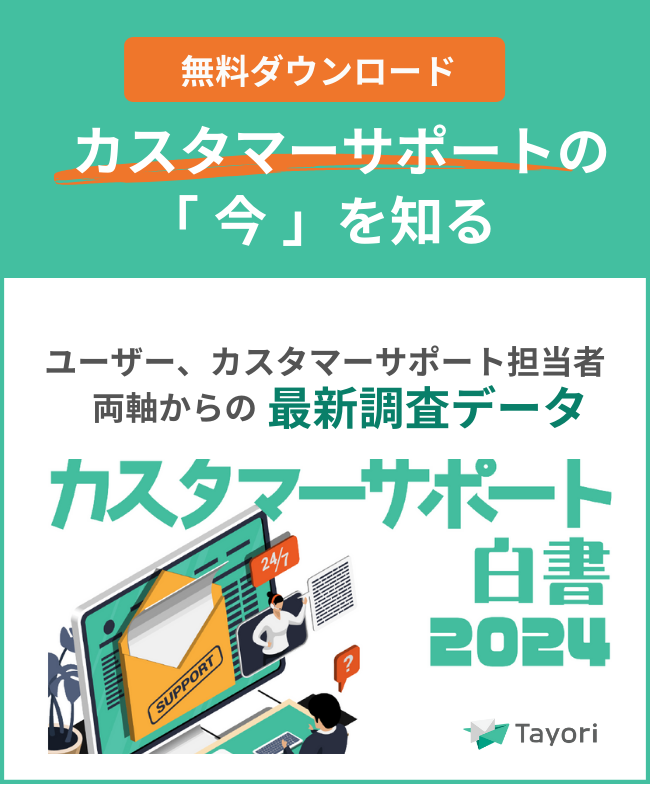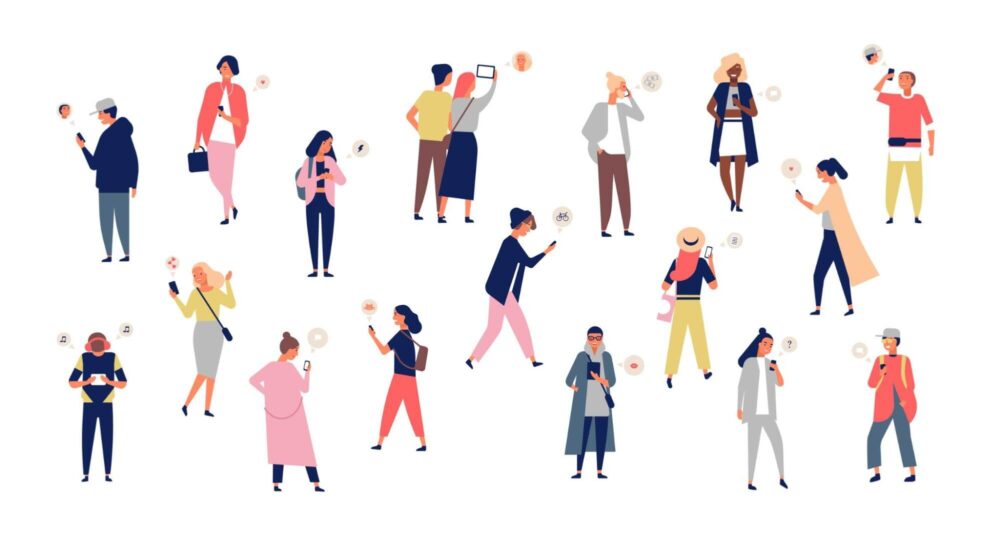【コミュニケーションツールの選び方】運用のコツも紹介

テレワークの導入や働き方の改革に伴って仕事で使用するコミュニケーションツールの重要性が高まってきています。
しかし仕事で利用するコミュニケーションツールは多数あるため、自社でどのようなツールを使用すべきか悩む人も多いのではないでしょうか。
本記事では、コミュニケーションツールを選ぶポイントと、コミュニケーションツールのメリットや運用のコツを紹介します。
ビジネスにおけるコミュニケーションツールとは
コミュニケーションツールとは社内や顧客との間で使用する、意思や情報の伝達を目的としたツールです。
ビジネスを円滑に進めるためには、スムーズなコミュニケーションが欠かせません。
近年では多数のコミュニケーションツールがリリースされており、「ビジネスのやり取りは電話かメールのみ」という会社は少なくなってきました。
社内用だけでなく、社外の人ともコミュニケーションツールを使ってやり取りをしている会社も増えています。
メールで良いのでは?
わざわざコミュニケーションツールを使わなくても、社内外でのコミュニケーションはメールでいいのでは?と思う人もいるかと思います。
しかし電話に比べて手軽なメールとはいえ、挨拶文を入れる必要があるなどメールでのマナーも重視されがちです。
その点コミュニケーションツールでは、メールよりも更に手軽に気軽に意思疎通ができリアルタイムでのやりとりが可能です。
法人向け・個人向けの違い
個人で使用する主要なコミュニケーションツールといえばLINEなどのSNSですが、ビジネスでのコミュニケーションツールではビジネスならではの特徴があります。
双方ともに機能面では大きな違いはありませんが、セキュリティが強化されていたり管理者権限プランがあったりと、チームや企業として使用できる工夫がされています。
そのためビジネスで使用する場合はビジネス専用のコミュニケーションツールを選ぶ必要があります。
コミュニケーションツールではどんなことができる?
コミュニケーションツールの機能は様々で、メールでやり取りをするよりもカジュアルにコミュニケーションが取ることができます。
- タスク管理機能
- ファイル・データ共有機能
- 通話・オンライン会議機能
- チャット・グループチャット機能
上記のように便利な機能が豊富にあるためそれぞれ解説していきます。
タスク管理機能
テレワークの大きな課題としてチームや個人でのタスク管理やスケジュール管理があると思います。
多くのコミュニケーションツールでは一人一人のタスクやスケジュールが把握できる機能があるため、個人ではもちろんチームとして業務の進捗状況がわかりやすくなります。
ファイル・データ共有機能
メールと同じくファイルやデータの共有も可能です。
とはいえ、メールでは基本的に一対一でのやり取りになるため、ファイル共有も一対一での共有になる場合が多いです。
ツールを使うと一対一での共有はもちろん、チームやプロジェクトごとのグループチャットなどを使用し共有したい人全員に共有が可能です。
通話・オンライン会議機能
文字だけのやり取りでは不十分な場合、電話を使うことが多いかと思います。
しかし電話を使用すると回線の問題や番号を入力するといった手間が発生しますよね。
そんな時に使用したいのがコミュニケーションツールの通話・オンライン会議機能です。
LINEと同じくワンタッチで通話できる他、グループで顔を合わせてコミュニケーションを取りたい場合に最適です。
テレワークを導入する企業が多くなった昨今では、顔を合わせて会話できるツールでのオンライン会議機能が必須となってきています。
チャット・グループチャット機能
近年ではメールでのコミュニケーションよりチャットでのやりとりが主流になりつつあります。
ChatWorkやSlackを中心にチャット形式のコミュニケーションに注目が集まっています。
メールのように挨拶文などの形式ばったツールより手軽に利用ができる他、コミュニケーションがリアルタイムに近い状態なのでスピード感のある情報共有が可能です。
またほとんどのツールではグループチャット機能が付いており、会社全体はもちろん部署やチームごとにグループを作成し、グループ内でチャット形式でのコミュニケーションが可能です。
テレワークが進む昨今では、メールよりも手軽で素早くコミュニケーションが取れるチャットは必須と言えるでしょう。
コミュニケーションツールを選ぶ4つのポイント
コミュニケーションツールは多くの種類があり、何をを選ぶべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。
この章では、コミュニケーションツールを選ぶポイントを紹介します。
操作が簡単で使いやすいツールを選ぶ
コミュニケーションツールは、円滑にコミュニケーションをとるために利用するものです。
使いこなせないメンバーがいる場合、ツール以外の方法でコミュニケーションを取ることになってしまい、最終的にツールが使われなくなったり、ツールが複数になり複雑になってしまったりする可能性があります。
コミュニケーションツールを導入する時には、メンバー全員が使いこなせることが重要なポイントです。
英語が苦手なメンバーが多いのに対し、日本語対応されていない海外のコミュニケーションツールを選んだことで、使い方がわからず失敗する事例もあります。
利用するメンバーに合わせて操作しやすいツールを選びましょう。
問題を解決できる機能があるツールを選ぶ
コミュニケーションツールを選ぶ2つ目のポイントは「自社のコミュニケーションに関する問題を解決できる機能があるツール」を選ぶことです。
- 「タスクを伝える方法がメールや口頭などバラバラで数も多く、何を伝えたのか・期限がいつだったのかがわからなくなっている」という場合は、Chatworkのようなタスク管理機能もあるツールを選び、窓口を1つにすることで解決できます。
- 「外部の人とのやり取りが多く、同時並行しているプロジェクトも多いため、メールを探すのも大変」という場合は、プロジェクトごとにスレッドを分けられるSlackのようなツールを利用するとツールを1つにまとめることが可能です。
公開する範囲も指定できるため、外部の人を入れてやり取りをしたい場合も安心です。
このように現在のコミュニケーションにおける問題を把握して、解決できる機能があるツールを選ぶことがおすすめです。
アプリの使用は可能か
コミュニケーションツールのアプリがあればパソコン以外からの使用も可能です。
アプリの使用が可能であれば外出先や在宅勤務時にも素早くコミュニケーションが取れる他、すぐに確認したいファイルや共有したいファイルを場所を選ばずアプリで完結できます。
アプリ使用の可否は仕事のスタイルや職場環境によっては重要なポイントの一つです。
費用面を確認する
コミュニケーションツールには無料有料問わず幅広いサービスが展開されています。
無料や格安のツールだったとしても、オプション料金を支払うことで使用できるサービスが追加できるツールなどもあります。
予算の範囲内で、必要な機能を兼ね備えたツールを選ぶようにしましょう。
コミュニケーションツールを使いこなす3つのコツ
コミュニケーションツールを導入したものの、上手く使いこなせず放置してしまっては意味がありません。
最後にコミュニケーションツールを使いこなすための3つのコツを紹介します。
操作方法を説明する機会を設ける
新しいコミュニケーションツールを導入する場合は、全員に操作方法を説明する機会を設けましょう。
「使ったらわかるだろう」と思う場合でも、メンバーによって理解度は異なるものです。
基本的な操作方法を説明して、ツールを使うことへの抵抗をゼロにしておきましょう。
盛り上げ役を作りツールに慣れてもらう
メンバーが新しいツールに慣れていない最初の時期には、社内で影響力のある盛り上げ役を作って積極的にツールを利用してもらえるようにすることもポイントです。
ツールの操作に慣れているメンバーや、普段から盛り上げ役のメンバーに頼むこともおすすめです。
ツールを使う頻度を増やしたり、新しい機能を使ってみたりするなどして、ツールに慣れてもらうきっかけを作りましょう。
ルールとしてツールの使用を促す
会社全体で特定のツールの導入を決定し、今後のコミュニケーションは、選んだツールで一元管理するという方針・ルールを徹底することも一つの方法です。
導入の際のサポートはあるという前提で、ある程度の強制力がないと、会社全体としてのツールの導入は難しい場合があります。
ルールとしておくことで、ツールの使用を促すための有効な手段となります。
NGルールを決めておく
新しいコミュニケーションツールを利用するときには、NGルールを決めておくことも大切です。
「◯◯をしないといけない」といったルールを決めるとルールが多くなってしまい、ツールを使うことが面倒になることも。
そのため、「これだけはNG」といった、してはいけないことだけを決めておく方がシンプルでわかりやすくなります。
「情報漏えいを防ぐため、社外ではツールを開かない」「社外秘の内容もあるため、社外の人をツールに入れる場合、全プロジェクト見られる権限は与えない」など気をつけるべきNGルールを決めておきましょう。
CSにおすすめのコミュニケーションツールはTayori
コミュニケーションツールは、ChatworkやSlack、Messengerなど様々ありますが、カスタマーサービスチームには株式会社PR TIMESが運営する「Tayori」も併用して利用することがおすすめです。
Tayoriは、チャットサービスやお問い合わせフォームとして利用できます。顧客からの問い合わせ内容ごとに、担当者やステータス・優先度を設定できたり、コメントを残せたりするためスタマーサービスチームのコミュニケーションを円滑に進めることができます。
「全社でのやり取りはSlackを利用しているので、Slackでお問い合わせ内容が見られたらいいな」という場合は、Tayoriの外部連携機能を利用することで実現できます。顧客のお問合せまでコミュニケーションツールで一元管理できるのは、見逃すことも減りとても画期的です。
求める機能がすべて揃ったコミュニケーションツールを見つけるのは難しいものです。外部サービスと連携して、チームにあった機能を追加してみてはいかがでしょうか。