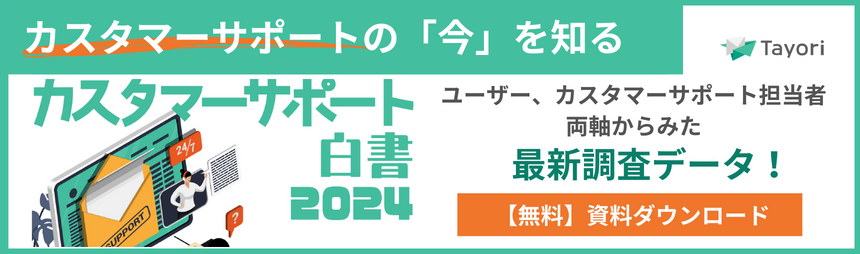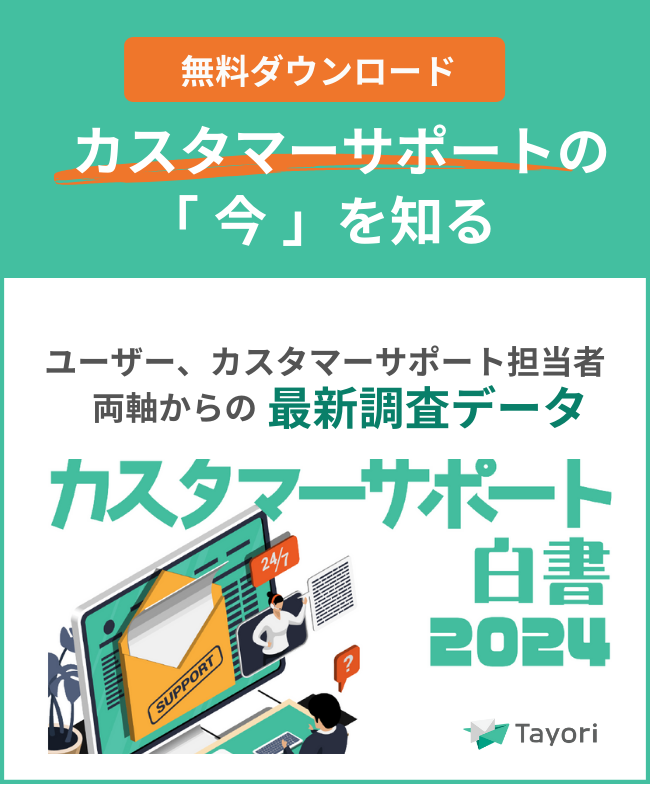健康経営とは?背景・メリット・デメリット・行うべき企業の特徴

近年注目を浴びている「健康経営」についてご存知でしょうか。
本記事では、健康経営についての基礎知識を徹底解説。健康経営が注目されている理由や、行うメリット・デメリットなどを紹介いたします。
「従業員の健康管理を行いたい」と検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
健康経営とは?
「健康経営」と聞くと、どのような内容を想像しますか?まずは、健康経営の意味から確認してきましょう。
健康経営の意味
健康経営は、アメリカの経営心理学者であるロバート・ローゼン氏によって提唱されたもの。
経済産業省によると、健康経営とは以下のように規定されています。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること
参照:経済産業省
従業員が健康であることが企業にとってもメリットがあり、リスクマネジメントにもなることから「従業員の健康管理を、経営戦略として行う」ことが健康経営だといえます。
不健康経営とは
遅くまで残業が続いて睡眠時間が十分にとれない、休みが取りづらいなどの社内環境の場合は、健康が害される可能性があります。
このような「健康経営」とは逆の状態を「不健康経営」と呼ぶことがあります。
不健康経営が続くと、従業員のモチベーションが下がったり、生産性が下がったり、離職が増えたりと負のスパイラルに入ってしまいます。
残業代が高くなったり、採用コストが高くなると、従業員の健康のために投資することも難しくなってしまいます。負のスパイラルに入る前に、健康管理をすることが求められるといえるでしょう。
健康経営優良法人とは?
経済産業省では、健康経営を普及・促進するために「健康経営優良法人認定制度」の設計を行っています。
「健康経営優良法人」として認定することで、健康系に取り組んでいる法人を見える化を図っています。
健康経営優良法人の認定基準
経済産業省による、健康経営優良法人を認定する項目は大きく分けて5つの項目があります。
1つ目は、「経営理念」。健康宣言を社内外に発信していることや、経営者自身が健康診断をしていることが求められます。
2つ目は、「組織体制」。健康づくりのための担当者を設置していることが判断基準となります。
3つ目は、「制度・施策の実行」。以下の15の項目が判断基準となります。
【従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討】
1.定期健診受診率(実質100%)
2.受診勧奨の取り組み
3.50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
4.健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
【健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント】
5.管理職又は従業員に対する教育機会の設定
6.適切な働き方実現に向けた取り組み
7.コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み
8.病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(15以外)
【従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策】
9.保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
10.食生活の改善に向けた取り組み
11.運動機会の増進に向けた取り組み
12.女性の健康保持・増進に向けた取り組み
13.従業員の感染症予防に向けた取り組み
14.長時間労働者への対応に関する取り組み
15.メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
大企業の場合は上記のうち12項目、中小企業の場合は7項目以上が当てはまっている必要があります。
4つ目は、「評価・改善」として、40歳以上の従業員の健診データの提供が求められることも。
5つ目は、「法令遵守・リスクマネジメント」として、従業員の健康管理に関する法令について重大な違反をしていないことが自己申告で求められます。
認定基準については、経済産業省の「健康経営優良法人の申請について」にも詳しく記載されているので確認するといいでしょう。
健康経営に関する助成金
健康経営は政府から推奨されており、導入にあたって様々な助成金制度が実施されています。
<助成金の一例>
多くの種類があるので、助成金について気になる方は、厚生労働省のホームページから確認することがおすすめです。
健康経営が注目されている背景
政府も推奨している「健康経営」。助成金を整備してまで推奨されているのには、どのような理由があるのでしょうか。
労働人口が減っている
健康経営が注目されている背景のひとつとして、「労働人口が減っている」ことが挙げられます。
企業にとっても、そして国にとっても労働人口を確保することは、発展していくために欠かせない要素です。健康な労働人口を確保することは、企業や国にとっての利益にも繋がるため、健康経営が注目されているのです。
長時間労働などのブラック企業
また、残業や休日出勤などの長時間労働が多い「ブラック企業」が社会的に問題になっていることも、健康経営が注目される理由のひとつです。
健康経営を行うことで、当然ブラック企業とよばれるような働き方をすることは減っていきます。
ワークライフバランスを重視する人が増えている中、長時間労働や残業、休日出勤がある企業は、これまで以上に人材の獲得が難しくなっています。
労働者にとってより働きやすい環境を整えることの必要性が高まっていることも、健康経営が注目されている背景だといえるでしょう。
関連記事:ワークライフバランスとは?定義・取り組み事例・ワークライフインテグレーションとの違い
健康経営を実施するメリットとは?
健康経営を実施するメリットについて、なんとなく把握できた方も多いでしょう。次に、健康経営を実施する具体的なメリットについて確認していきましょう。
1.企業のイメージが向上する
健康経営を実施する1つ目のメリットは、企業のイメージが向上することです。
健康経営に積極的に取り組んでいる企業は、「従業員のことを大切に考えている」「労働環境が整っている」「福利厚生が充実している」といった好印象を与えられるため、企業のイメージの向上に繋がります。
2.生産性を上げられる
健康経営を実施する2つ目のメリットは、生産性の向上です。
社員の健康状態は仕事の生産性に大きく関わります。健康的に仕事に取り組める可能性が上がるほど、モチベーションや生産性も上がることが期待できます。
3.リスク管理を行える
健康経営を実施する3つ目のメリットは、リスク管理を行えることです。
「管理職として育てていた社員が病気の治療に専念するために退社する」「健康上の理由で休職する」といった健康上の理由での休職・退職は企業にとってのリスクだといえます。このようなリスクを健康経営を行うことである程度管理し、防止できることも、健康経営のメリットだといえるでしょう。
4.離職率を改善し、優秀な人材獲得に繋がる
健康経営を実施する4つ目のメリットは、離職率の改善や、優秀な人材の獲得に繋がることです。
健康上の理由での離職率を減らせるだけでなく、労働環境が整うことから離職率の改善や優秀な人材の獲得に繋がる可能性もあります。
健康経営を行うことでデメリットはあるの?
企業は従業員一人ひとりの集合から成り立っています。従業員を企業の財産と考え、健康管理をすることで多くのメリットがあることはすでに把握できたでしょう。
健康経営を行うことは、メリットばかりのようにも見えますが、これらのメリットは「効果検証がしにくい」ことに注意が必要です。
健康経営に投資をしても、投資の効果が出ているのかを明確に把握することは困難です。そのため、予算をどの程度活用してもいいのか判断しにくいことがデメリットとして挙げられます。
また、健康経営を実施するためにはある程度の予算が必要なこと、タスクが増えることで企業だけでなく従業員の手間にもなること、そしてプライベートな情報を会社に把握されることに抵抗を感じる人もいることは把握しておきましょう。
健康経営を行うべき企業の特徴
これまで、健康経営のメリットやデメリットを紹介してきました。
健康経営はすべての会社で導入するメリットがある制度です。特に、「労働環境が整っていない」「従業員の健康状態が好ましくない」という場合は、健康経営を行うメリットが大きいといえるでしょう。
健康経営を行うために社内制度を見直そう
「健康経営を行いたいたけれど何から手を付けたらいいのかわからない」という場合、まずは業務の効率化や仕組みを整えることがおすすめです。
業務の効率化が整うことで、労働時間の短縮に繋がりますし、心身ともにストレスを軽減できるので従業員の健康状態の改善にも繋がります。
株式会社PR TIMESが運営する業務効率化ツール「Tayori」を活用すると、部署間でのタスク管理がより確実に、スムーズに行なえます。
業務効率化ツールとして、Tayoriを活用する主なポイントは以下の7つです。
①部署間の業務依頼を問い合わせフォームから行うことで、必要な情報を確実に送付してもらう(例:営業部門が経理に請求書の修正依頼をする場合)

導入事例:請求関連問い合わせをフォーム経由に一本化。フォーム横にFAQを並べ対応の手間を激減
②情報収集の紙媒体をフォームに代替してペーパーレス化し、収集した情報はCSVでエクスポートして管理
③定型の情報の記録にフォームを活用。報告書のフォーマット(日報や週報・面談記録など)として活用、電話対応履歴をフォームに入力して、受信箱に記録を残す
④FAQ機能を活用して、情報を一箇所にストック化、社内の情報共有ページとして活用

導入事例:PR TIMES 当社テレワーク対応
⑤チームのナレッジを集めて蓄積するナレッジベースやマニュアルページとして活用
タグを設定することも可能なので、従業員が「健康診断について知りたい」など特定の内容を確認したい場合、キーワードを入れて簡単に検索できます。
⑥商品やサービスが多岐にわたる場合にサービス・製品の紹介ページとしてFAQページを活用。マーケティングの一環としてページを簡単作成
⑦FAQページに社内の各部署への業務依頼のフォームを設置(例:総務部に対して、名刺発行を依頼するフォーム)
「社内依頼時に必要な項目を揃えて依頼してほしい」「部署ごとにタスク管理を行いたい」「社内マニュアルを作成したい」という場合に、業務効率化ツールTayoriは特に効果を発揮するでしょう。
無料から使える機能もあるので、ぜひ一度ご確認ください。