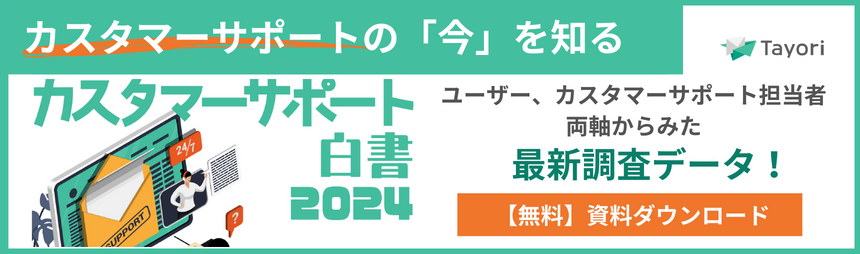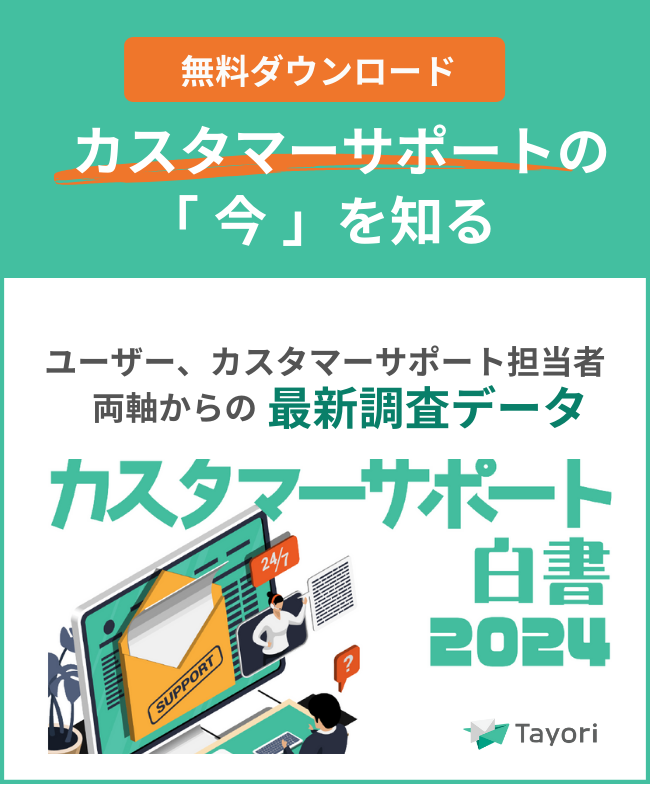「マニュアルを読んでくれない」
「いつも同じ質問ばかりされる」
「質問の回答に手間が取られて業務が進まない」
このようなお悩みはありませんか?
こういったお悩みを解決する策として「ナレッジベースとして社内FAQサイトを作ろうかな」と検討している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、社内FAQサイトを作成する効果から、作り方のポイント、そして失敗してしまうケースについて紹介します。
「せっかく社内FAQサイトを作ったのに使わなかった……」ということにならないように、社内FAQサイトの作成を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
社内FAQとは?
そもそも社内FAQって具体的にどういうシステムなの?という疑問に対して簡単に説明しておきます。
社内FAQとは、社内各所から担当部署や担当者に寄せられる質問を「よくある質問」として用意しシステム化することを指します。
会社の規模が大きくなればなるほど、人の数はもちろんルールや制度の数も増えてきますよね。
それに伴い、制度を把握できていない社員や制度に関しての質問も増えてきます。
社内各所からの質問対応に追われ本来するべき業務ができないなど、支障を来す場面もあろうかと思います。
社内FAQはそんなお悩みを解決してくれる便利なシステムです。
社内での問い合わせ対応などの負担を減らしたり、社内制度の把握や手続きをできる限り自己解決してもらいたい時に導入してみると良いでしょう。
FAQとQ&Aの違い
FAQは「Frequently Asked Questions」の略で、よくある質問を意味します。
一方、Q&Aは「Question & Answer」の略で、質問とその回答を意味します。社内FAQは、企業内でのよくある質問をまとめたものであり、Q&Aは一般的な質問とその回答をまとめたものとなります。社内FAQは、特定の業務や業界に特化した質問を集めたもので、Q&Aは幅広いジャンルの質問を扱うことが多いです。
社内FAQサイトを作る5つの効果・メリット
まずは、社内FAQサイトを作る効果やメリットを確認しておきましょう。
1.現場スタッフの教育コストの削減
社内FAQサイトを作る1つ目のメリットは、現場スタッフの教育コストを削減できることです。
業務をしていくにあたって、「こんなときはどうやって対応したらいいんだろう」と小さなが疑問がいくつも出てきますよね。「毎回質問をしていて、先輩の時間を奪っている気がする」「マニュアルのどこかにあるらしいけれど、どこにあるのかがわからない」という場合、現場スタッフの教育にかかる時間的なコストは大きくなってしまいます。
社内FAQサイトがわかりやすくまとまっていることで、疑問に思ったことは自分自身で解決できるため、教育コストの削減に繋がります。
2.業務の効率化
社内FAQサイトを作る2つ目のメリットは、業務の効率化です。
先ほどの内容にも共通しますが、マニュアルがあってもどこを見たら答えがあるのかわかりにくい場合「マニュアルを探している時間が発生する」「コミュニケーションコストが発生する」ことになります。本来なら必要ない時間を削減できることで、業務の効率化に繋がります。
効率化できる部分の時間短縮をすることで、本来注力するべき重要度の高い仕事にコミットできるようになるでしょう。
3.知識の整理
社内FAQサイトを作る3つ目のメリットは、作成者自身も知識の整理ができることです。
社内FAQサイトを作成するときには、業務を網羅的に整理していく必要があります。そのため、作成していくうえで「この部分がわかりにくいんだな」「マニュアルにはこの部分が抜けていたな」と気づけることもメリットです。
作成者自身も、より深く業務について理解することで、必要のないフローはないのか、もっと効率化できる部分はないのか確認できます。
4.問題をスピーディーに解決
社内FAQサイトを作る4つ目のメリットは、問題をスピーディーに解決できることです。
社内FAQを利用することで、発生した問題や疑問を迅速に解決することができます。これにより、業務の遅延を防ぐことができ、顧客への対応もスムーズに行うことができます。
5. ナレッジを蓄積し、属人化を防止
社内FAQサイトを作る5つ目のメリットは、属人化の防止につながることです。
従業員が退職すると、その人が持っていた知識や経験が失われることがあります。しかし、社内FAQを活用することで、そのような知識や経験を蓄積し、属人化を防ぐことができます。これにより、企業の知識資産を継続的に活用することができます。
社内FAQサイトが失敗してしまうケース
社内FAQサイトを作成することはメリットばかりのように思えますが、実は失敗してしまうケースもあります。
実際に社内FAQサイトを作成して失敗してしまうケースはどのようなケースなのか事前に確認しておきましょう。
ケース1.そもそも情報が少ない
社内FAQサイトが失敗する大きな原因は「そもそもFAQに入っている情報が少ない」ことです。せっかくFAQページを見ても、求めている答えが探し出せなければ、FAQページを見ることはなくなります。
「基本的な内容だからわかるだろう」「これは別のページにあるから……」と省くのではなくて、今後利用する人は業務の事前知識がまったくないものだと想定して、細かく情報を網羅的に入れるようにしましょう。
ケース2.情報がどこにあるのか探しにくい
情報が網羅的に入っていても、社内FAQサイトが失敗するケースが「情報が探しにくい」ことです。
探したらどこかに答えはあるはずだけれど、フォルダが複雑で見つけ出せない、キーワードで調べたら無限に出てきて求めている内容を見つけるのに時間がかかる……。このような状態だと「社内FAQサイトで探すよりも、わかる人に聞いたほうが早いな」となってしまいがち。
どれだけスタイリッシュなデザインでも、どれだけ多機能でも、そもそも使いにくければ意味がありません。せっかく導入して情報もたくさん入れているのに使われない……といった悲しい結果にならないように、誰でも簡単に活用できるようにすることが重要です。
ケース3.情報が古くて使えない
情報が網羅的にあって、検索性も高いけれど「そもそも入っている情報が古くて使えない」というケースもあります。
導入時に内容を更新してから、その後業務内容は変わっているのに、社内FAQサイトの内容は更新されていないまま……となっているケースも意外と多いもの。情報が古い場合、情報がないのと同じことです。後ほど詳しく紹介しますが、情報は定期的に見直すことが重要です。
社内FAQの作成に活用できるツールの種類
社内FAQのメリットはわかったし運用していきたいけど、いまいちイメージが掴めない、何から始めていいかわからない。
そういった場合はまず、どのツールを利用して社内FAQを作成するかを決めましょう。
この章では社内FAQツールの種類を解説していきます。
1.エクセル
社内FAQツールとして一番手軽に始められるのがエクセルです。
社内PCに入っているエクセル機能を使い、質問と回答を入力するだけである程度仕上がります。
とはいえ、エクセルを使用すると検索機能が心細い他、できることが限られてくるためボリュームが大きくなった時に使いづらくなったり重くなったりする可能性があります。
2.チャットボット
チャットボットは顧客向けに使用されることが多いですが社内FAQとしても使用できます。
チャット形式のFAQで、わからないことをチャットに入力するとその答えが返ってくるという仕組みです。
この方法は簡単ではありますが、検索機能がないため自分で探すということができず、答えに辿り着くまでに時間がかかってしまうというデメリットがあります。
3.ナレッジベースツール
ナレッジベースツールとはFAQ作成はもちろん、社内の情報共有にも最適なツールです。
社内FAQに必要な便利な機能が付いており、手軽に簡単にわかりやすい社内FAQを作成するのにぴったりです。
ナレッジベースツールを提供している企業は複数ありますが、予算や機能に応じて選ぶと良いでしょう。
社内FAQを作成するツールの選定ポイント
社内FAQの導入に際して、最も重要なのは「どのツールを選ぶか」という点です。適切なツールを選ぶことで、FAQの作成や運用がスムーズに行えます。以下に、ツール選びの際のポイントをいくつかご紹介します。
使いやすさ
初めての導入であっても、直感的に操作できるインターフェースが求められます。
特に、カスタマーサポートや営業などの窓口が多岐にわたる企業や、マルチタスクをこなす個人事業主や中小企業の方々にとっては、簡単に使えるツールが必要です。
カスタマイズ性
企業のニーズや業務内容に合わせて、FAQのデザインや機能をカスタマイズできるかどうかを確認しましょう。
例えば、特定のキーワードでの検索機能や、関連するFAQの表示機能など、必要な機能を自由に追加できるツールがおすすめです。
更新の容易さ
FAQは定期的に更新する必要があります。そのため、情報の追加や編集が簡単にできるツールを選ぶことが重要です。また、複数の担当者が同時に編集できる機能も、大きなメリットとなります。
セキュリティ
社内情報を扱うため、セキュリティ面での信頼性が求められます。ツールのセキュリティ対策や、情報漏洩のリスクを最小限に抑える機能が備わっているかを確認しましょう。
サポート体制
何か問題が発生した際に、迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかも重要です。ツールの公式サイトやユーザーレビューを参考に、サポートの質を確認することをおすすめします。
社内FAQ作成の手順
どのシステム、どのツールで作成するか決定したら、実際に社内FAQを作成していきます。
とはいえ、日々、数多く寄せられる質問や制度ルールをわかりやすく見える化するのは難しいですよね。
この章では社内FAQ作成の手順をわかりやすく解説していきます。
1.よくある質問をリストアップ
まずは社内から寄せられる「よくある質問」をリストアップしていきましょう。
この時のコツとして、できるだけ細かくジャンル分けすることをおすすめします。
細かくジャンル分けすることで、完成した時に探しやすく見やすい仕様になります。
漠然とした質問ではなく、実際に社内から寄せられるリアルな質問や細かい質問等できるだけ多くをリストアップしていきます。
2.リストアップした質問の回答を作成
次にリストアップした質問の回答を作成していきます。
社内FAQは社員自身が自己解決できる手助けをするツールなので、できるだけわかりやすく易しい言葉を使って回答を作成しましょう。
また、回答を作成する中で別の質問として用意した方が良い事柄が出てくる場合は、新たに質問と回答を用意するとわかりやすいFAQとなります。
3.完璧な状態でなくても運用していく
質問と回答がある程度仕上がってきたら実際に運用していきましょう。
良くありがちなのが完璧なコンテンツを目指すばかりに、ボリュームだけが膨れ上がっていきシステムとしての使いやすさや機能のバージョンアップがされないことです。
そのため未完成でも見切り発車でも、ある程度のコンテンツに仕上がってきたら試運転としてシステムを運用していきましょう。
試運用としてシステムを動かしていくうちに、各所からの指摘を参考に少しずつコンテンツの改善をしていきます。
「別に完成してから運用しても改善はできるよね?」そう考える方もおられると思いますが、ボリュームが増えれば増えるほど、変更箇所も膨大になっていきます。
そのためシステムの改善をしつつ、コンテンツの充実をしていくことをおすすめします。
4.都度、更新して完成させる
社内FAQを運用している間にも、社内FAQだけでは解決できない質問等が寄せられるので、臨機応変に変更・更新していきましょう。
新しく社内ルールが決まった際や変更があった場合にも社内FAQを変更・更新していきます。
社内FAQサイトの作り方・運用のポイント
社内FAQサイトは、日々のメンテナンスなしには失敗してしまうことがわかりました。では、社内FAQサイトを実務で活用していくためには、どのようなポイントに注意すればいいのでしょうか。
ポイント①:誰でも気軽に更新できるようにする
まずは、情報を最新のものにするため、そしてよりFAQを充実させるために「誰でも気軽に更新できるようにしておく」ことがポイントです。
どのような情報がほしいのか、またどの情報が古くなっているのかは、実際にFAQを活用している現場スタッフが1番詳しいでしょう。実際にはFAQを使用していない一部のマネージャーたちだけがFAQを作成できるようにするのではなく、メンバー全員が更新できるような仕組みにしておくことで、コストをかけずに情報更新できます。
例えば、FAQ作成ツールTayoriなら、誰でも簡単にFAQを作成・更新することができます。
「誰でも更新できるようにするのは心配……」という場合には、現場スタッフから「このページにこの内容を足したい」「このページをアップデートしてほしい」などの更新要望を受け、最終ファクトチェックをして情報更新をする責任者を立てることがおすすめです。
ポイント②:責任者を決めておく
「誰でも気軽に更新をすると、情報が正しいものかどうかわからなくなりそう」と心配な方もいらっしゃるでしょう。先ほどの内容と少々矛盾するように感じるかもしれませんが、社内FAQサイトの内容には「責任者を設定しておく」こともポイントです。
社内FAQに対して責任者がいない場合には、情報漏れや、情報が古くなっていることに気づいても「どうせ誰かが更新するだろう……」と当事者意識が欠けてしまいがち。責任者を立てることで、イチ業務として機能させやすくなります。
ポイント③:定期的に情報を見直す
現場スタッフによる更新や、責任者を決めて更新を促したとしても、やはり抜け漏れが出ることは避けられません。定期的に情報を見直す時間を取ることで、確実にFAQページをアップデートしていくようにしましょう。
カスタマーサポートツール「Tayori」で社内FAQサイトを作成しよう
社内FAQサイトを作成する際には、単に作成しただけで終わらず、その後更新し続けることが重要だとわかりました。
社内FAQツールの導入を検討している場合には、株式会社PR TIMESが運営するカスタマーサポートツール「Tayori」の「FAQ」がおすすめです。
Tayoriを活用すると、Webページ制作の知識がなくても、ドラック&ドロップの簡単な操作で、洗練されたページを制作可能。誰でも簡単に操作できるので、チームメンバー全員で情報をアップデートしていけます。
>>社内FAQサイトのサンプルはこちら
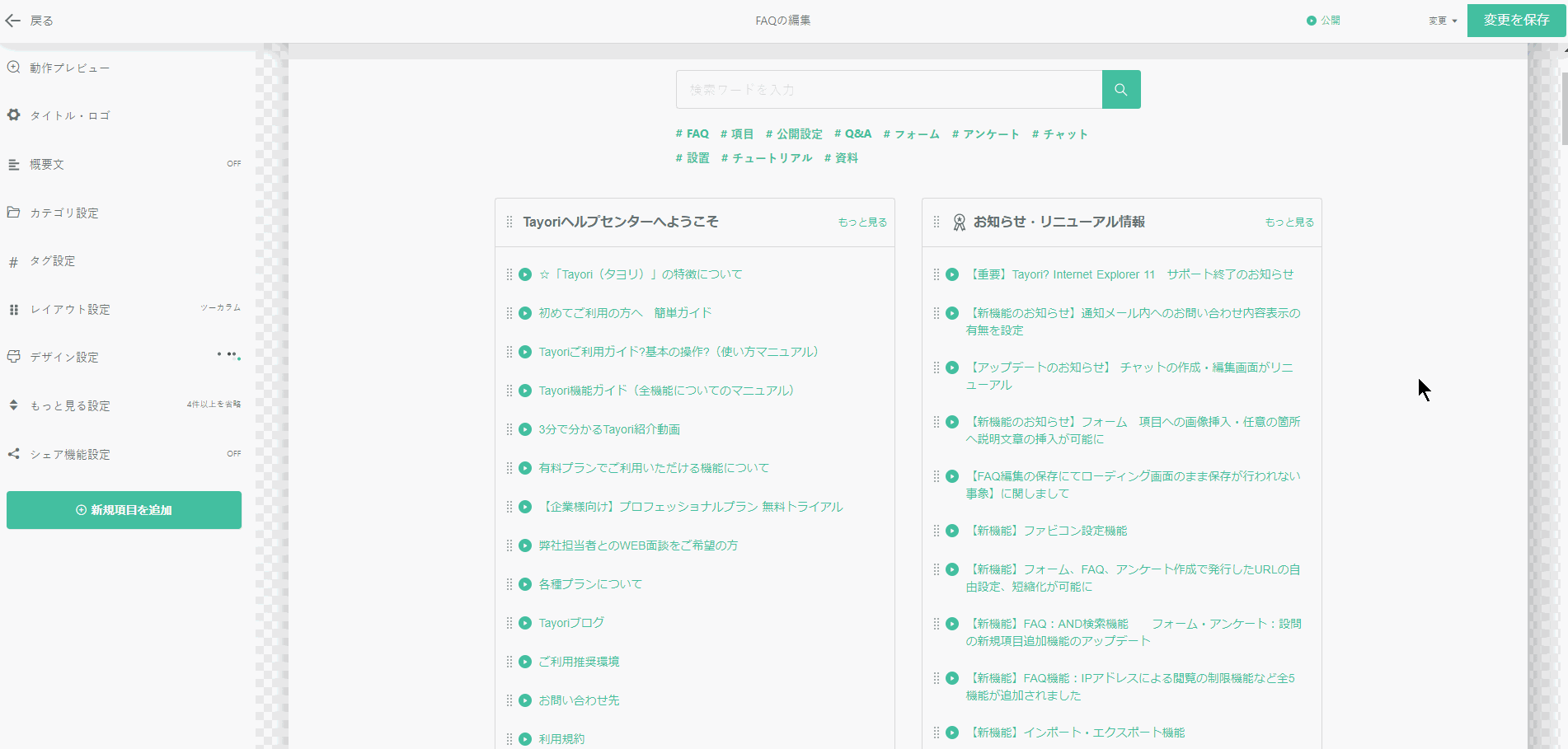
質問内容はカテゴリごとに分類したり、タグを設置したりできるため、検索性もバツグン。画像や動画も埋め込みできます。また、お問い合わせフォームや、チャットサポートとも連携できることもポイントです。
IPアドレス制限や、パスワードで閲覧制限ができるので、社内ナレッジベースとしても活用できます。
社内FAQや、ナレッジベースを作成したい方は、ぜひTayoriで作成してみるのはいかがでしょうか。
また、Tayoriの導入によって業務効率アップができるか、チームのでご利用に最適な有料プラン(プロフェッショナルプラン)の無料トライアルもぜひ一度体験してみてください。