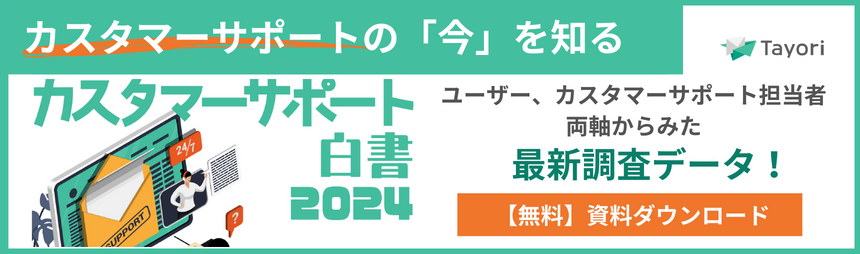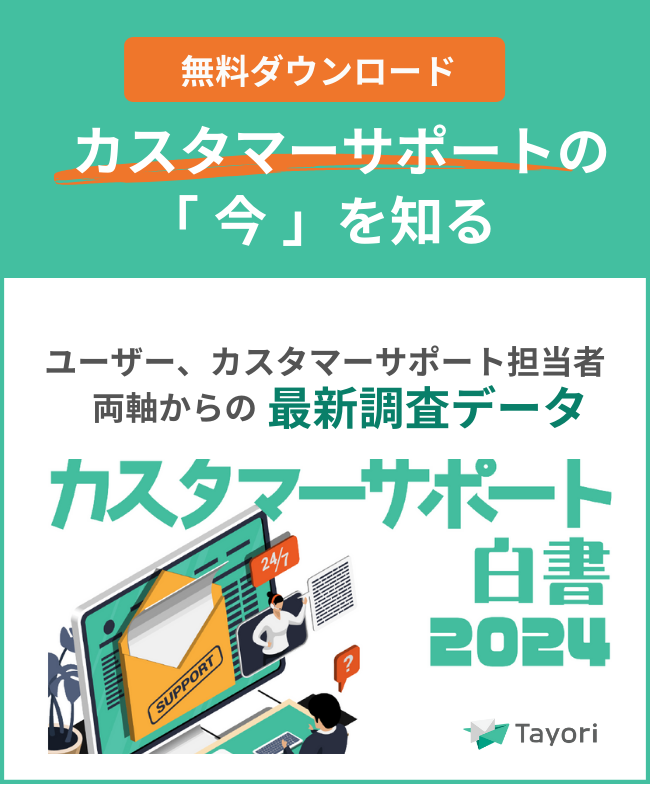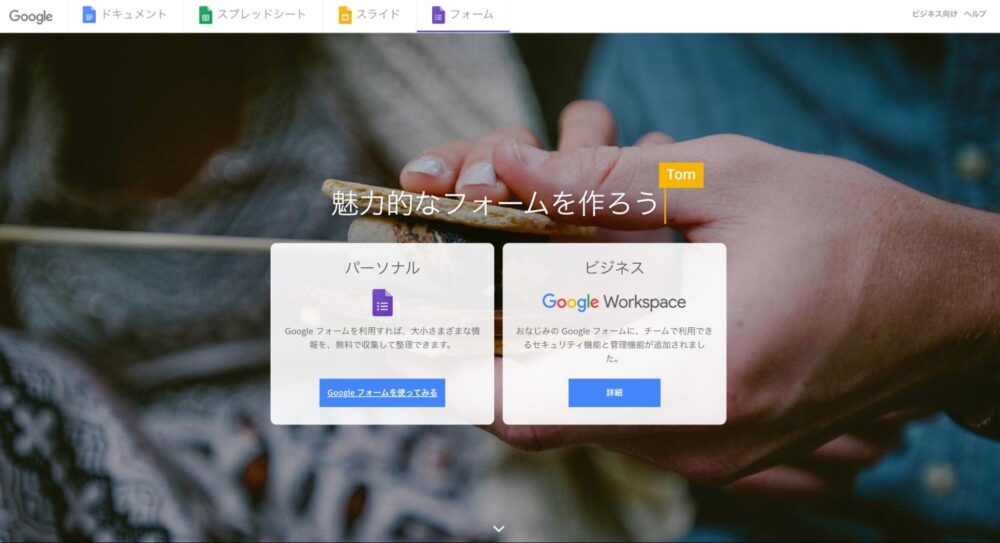社内で依頼をする機会は、思っている以上に多いもの。社内のメンバーに頼むときには、つい雑に依頼してしまい、依頼が思うように進まなかったり、頼まれた方もつい優先順位が低くなって忘れたりなど、何かと問題も発生しやすいこともあります。
頻度の多い社内依頼をスムーズに処理することで、大幅に業務改善します。
本記事では、社内で確実に依頼を行い、処理スピードを上げるための方法を紹介します。
社内で依頼する際によくある課題
社内にタスクを依頼するのは思っている以上に頻繁にあります。社外に依頼する際には緊張感を持って依頼、またタスクを実行できますが、社内に依頼する際にはどうしてもカジュアルになってしまいがちです。
まずは、社内に依頼をして失敗してしまうケースを確認してみましょう。
悩み1.ざっくりとした依頼で、要件が明確になっていない
社内に依頼をして失敗する1つ目の原因は、依頼の要件が明確になっていないことです。
社内のメンバーにタスクを依頼する際には「◯◯しておいて!」とざっくりと依頼をしてしまうこともあるでしょう。頼んだ本人にとっては、何をしてほしいのか明確だったとしても、頼まれたほうは「何のことかな?」「具体的に何をいつまでにしてほしいのかな?」と悩んでしまいがちです。
要件が明確になっていないことで、タスクが進められないケースも多く、タスク処理までに時間がかかってしまいます。
悩み2.依頼方法が混在する
社内に依頼をして失敗する2つ目の原因は、依頼方法が統一されていない点が挙げられます。
例えば、一部はメールで、あるいはSlackやTeamsで、さらには口頭でといったケースがあります。これにより、受け手は依頼がどこからくるのか予測がつかず、結果として重要な依頼を見落としてしまう可能性が高まります。
また、依頼の優先度が伝わりづらい場合もあります。電子メールは緊急性が高いと感じにくいため、その他の手段で急な依頼がくると、整理がつかなくなってしまう場合があります。
悩み3.口頭で頼まれたもの、優先順位が低いものを忘れてしまう
社内に依頼をして失敗する2つ目の原因は、タスクを失念してしまうことです。
社内依頼の場合、正式なワークフローで依頼されるのではなく、口頭で依頼されることもよくあること。口頭で頼まれた場合、失念しやすくなってしまいます。
また、自分の仕事が忙しい中、頼まれたタスクの優先順位が低くなってしまい、忘れてしまうケースも多々あります。
特に部署が違う依頼の場合、状況を把握しきれていないことで優先順位をつけにくく、タスク自体を失念しやすいことに注意が必要です。
悩み4.違う人へ依頼し直さないといけない
社内に依頼をして失敗する4つ目の原因は、依頼するべき人・部署が間違っていることです。
特に他部署への依頼をする際には、担当者を明確に把握していないことも多く、間違った人に依頼していることも少なくありません。依頼された側が、本来の担当者に依頼し直していることも多く、コストがかかることや、タスク漏れしてしまいやすいことが問題です。
社内の依頼によくある課題を解決する方法
次に、社内に依頼をして失敗しないための解決案を確認してみましょう。
解決案1. 要件が整理された状態で依頼を受け付けるフォームを設置する
要件が明確になっていない場合には、強制的に要件を整理するフォームを作成して、依頼を受け付けるという方法が有効です。
業務の依頼自体をフォームを作成しておけば、必要な情報は必須として入力が必要なため、要件整理ができていないという状態がなくなります。
解決案2.依頼のチャンネルを統一する
依頼方法が混在している問題を解決するためには、まず依頼のチャンネルを一つに統一することが有効です。例えば、「社内の依頼は全てメールで行う」といったルールを設定することで、受け手はどこで依頼が来るのかが明確になり、依頼を逃さなくなります。
依頼の方法を統一した上で、次に重要なのは依頼の優先度を明示することです。これにより、受け手はどの依頼から手をつけるべきかが明確になり、効率的にタスクを消化することが可能となります。
解決案3. 口頭でタスクを受け付けない、依頼する人は依頼ルートを守る
依頼のルートを一本化するように徹底する必要があります。例えば、口頭で業務の依頼を受け付けた場合には、ここのフォームより依頼をしておいていただけますか?と再度依頼ルート自体を伝えて、依頼ルートを守ってもらうようにするということです。
もしそれでも、依頼ルートを守らない人がいる場合には、直属の上長に注意してもらうようにするなど、対応を考える必要があります。
解決案4. 依頼するべき人・部署を明確に整理する
頻繁に発生する社内の依頼タスクに関しては、どの部署に、そして誰にどのように依頼するべきかということがまとまっている状態にすることが重要です。
例えば、社内FAQページ(ヘルプページ)を作成するなどして、社内タスクを一覧として表示しておくなどの工夫が有効です。
関連記事:社内FAQサイトの効果・作り方のポイントは?【失敗してしまう3つのケース】
社内の依頼をメールでお願いする場合のポイント
社内の依頼をメールで行う際に、正しく相手に情報を伝えるために重要なポイントを解説します。
件名は要件がわかるように記載する
依頼をメールで行う場合、最初に注意するべきは「件名」です。件名が曖昧だと、メールが開かれる可能性が低くなり、依頼がスムーズに進まない可能性が高いです。例えば、「資料について」という件名より、「7月度の営業成績資料作成依頼」という具体的な件名の方が理解しやすいです。
依頼内容を明確に記載する
依頼内容は短く、しかしながら十分に詳細な情報が含まれている形にすることが大切です。何を依頼するのか、その依頼にどういったデータや資料が必要なのか、必要なアクション項目を明確にする必要があります。例えば、資料作成の依頼であれば、「7月度の営業成績を集計し、資料を作成してください。集計方法は前月と同様です」というように具体的に記述するとよいでしょう。
依頼する理由を伝える
依頼の背景やその理由も明示することで、相手が納得しやすくなります。人は「なぜその作業が必要なのか」を理解すると、より協力的になることが多いです。短い一文で良いので、依頼する大きな目的やゴールを述べましょう。
期限を設ける
依頼には明確な期限を設定することが重要です。期限があいまいだと、そのタスクが後回しにされがちです。期限を明確にすることで、相手も計画を立てやすくなり、依頼がスムーズに運びます。
相手の状況を配慮し、丁寧な文章で依頼する
最後に、相手の状況を考慮して、依頼の文面を作成することが大切です。急な依頼や余裕のないスケジュールに配慮し、「もし可能であれば」といった柔らかい表現を使うとよいでしょう。
以上のポイントを踏まえて、メールでの社内依頼がスムーズに進むよう心掛けましょう。特にカスタマーサポートや営業など、多忙な部署で働いている方にとって、効率的な依頼方法は非常に重要です。
社内の依頼メールで使えるフレーズ
社内での依頼をメールで行う際には、相手に明確かつ丁寧に要件を伝えることが重要です。ここでは、依頼メールを書くうえで参考になるフレーズを紹介します。
依頼する時に使えるフレーズ
・〇〇に関してお願いがございます。
・お願い申し上げます。
・お願いいたします。
・〇〇いただければと存じます。
・ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
・お手数おかけしますが
・大変恐縮ですが
メールの締めに使えるフレーズ
・お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
・ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
・お手数をおかけしますが、ご対応いただけますと幸いです。
・お知らせいただければ幸いです。
・お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
・お力添えいただけましたら大変助かります。
・引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
依頼する時のNGフレーズ
依頼をする際に、意図せず相手に威圧感を与えるような表現や期限が曖昧なまま依頼をしてしまう場合があります。次のような表現や依頼の方法はできるだけ使わないようにしましょう。
・「すぐにやってください。」「願います」などの命令口調
・「早めに」「◯◯しておいて!」という曖昧な表現
・「できれば今日中に」など過度な要求をする
社内の依頼メールで使える例文
ここでは、依頼メールを書くうえで参考になる例文を紹介します。
資料作成の依頼メール
|
件名 7月度の営業成績資料作成のお願い 本文 〇〇部 〇〇さん お疲れ様です。〇〇部の〇〇〇です。 営業会議で使用する資料の作成をお願いします。 7月度の営業成績を集計し、資料を作成してください。 集計方法は前月と同様です。 以下に概要をまとめていますのでご確認をお願いします。 ・〇〇〇〇〇 ・〇〇〇〇〇 ・〇〇〇〇〇 もし可能であれば、〇月〇日(〇)までに作成いただければ幸いです。 難しい場合には調整しますので、お知らせください。 不明点があれば、私または△△△までご確認ください 。 ご確認のほどよろしくお願いいたします。 ————————————————– 〇〇部 〇〇〇 電話:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 メール:〇〇〇〇〇〇〇〇@〇〇〇〇〇 ————————————————– |
資料確認の依頼メール
| 件名
7月度の営業成績資料確認のお願い 本文 〇〇部長 お疲れ様です。〇〇部の〇〇〇です。 〇月〇日(〇)に行われる営業会議の資料をお送り致します。 詳細は添付のファイルをご確認ください。 お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただき、加筆・修正などございましたら、 〇月△日(△)までにお知らせいただければ幸いです。 ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 ————————————————– 〇〇部 〇〇〇 電話:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 メール:〇〇〇〇〇〇〇〇@〇〇〇〇〇 ————————————————– |
社内で確実に依頼をするにはメールはNG?
社内向けの依頼メールは、挨拶や宛名、署名などを含めるために作成に時間がかかり、非効率に感じられることがあります。複数人に対するメールのやり取りにおいて、情報の漏れや管理の困難さから本来の業務に支障が出る場合があるため、社内で確実に依頼をするには、業務効率化ツールの導入がおすすめです。
社内への依頼を確実に消化するためには「業務効率化ツール」がおすすめ
社内への依頼を確実に消化するためには、先ほど紹介したような問題が起こらないようにする必要があります。
そのためには、業務効率化をすすめることができるツールの導入がおすすめです。
今回は、株式会社PR TIMESが運営するカスタマーサポートツール「Tayori」を活用した際のメリットを確認してみましょう。
メリット1.必要な要件が揃った状態で依頼できる

業務効率化ツールを活用する1つ目のメリットは、必要な要件が揃った状態で依頼できることです。
依頼フォームを作成することで、必要な要件が揃った状態で依頼を受けられるため、コミュニケーションコストを削減できます。
メリット2.タスクが見える化される

業務効率化ツールを活用する2つ目のメリットは、タスクが見える化されることです。
ツールでタスク管理できるため、処理できていないタスクが一目瞭然。チームでのタスクも確認できるため、管理が簡単になります。
メリット3.簡単にエスカレーションできる
業務効率化ツールを活用する3つ目のメリットは、簡単にエスカレーションできることです。
業務効率化ツールを活用すると、タスクの担当者を設定できるため、エスカレーションすることも可能。また、依頼する際の宛先を設定したり、マニュアルを作成したりしておくことで、間違った宛先への依頼も防げます。
「Tayori」を活用し社内依頼を効率的に進めよう
社内依頼を効率的に進めるためには、「Tayori」の活用がおすすめです。
今まで社内依頼時に不便さを感じたことがある方は、「Tayori」を活用することで、タスク処理の時間や、コミュニケーションコストを大幅短縮されることを実感できるでしょう。
低コストで導入できるので「効率化したいけれどコストはかけられない」「導入に時間がかかるのは難しい」とお悩みだった社内業務にも気軽に導入できます。
無料から使える「Tayori」ですが、有料プランの機能を14日間無料で試せるトライアルも実施中です。
手間をかけずに効果的な申し込みフォームを運用したい方はぜひお試しください。
>>>トライアルに申し込む