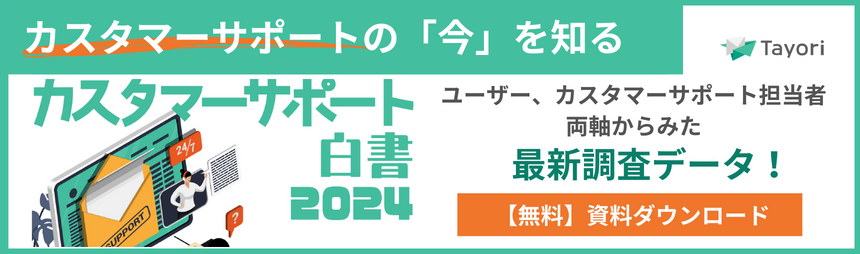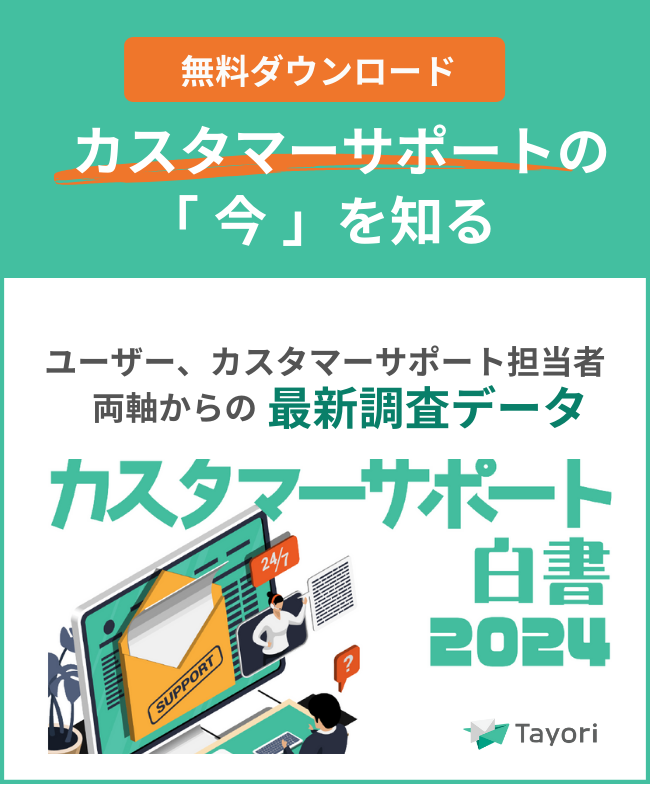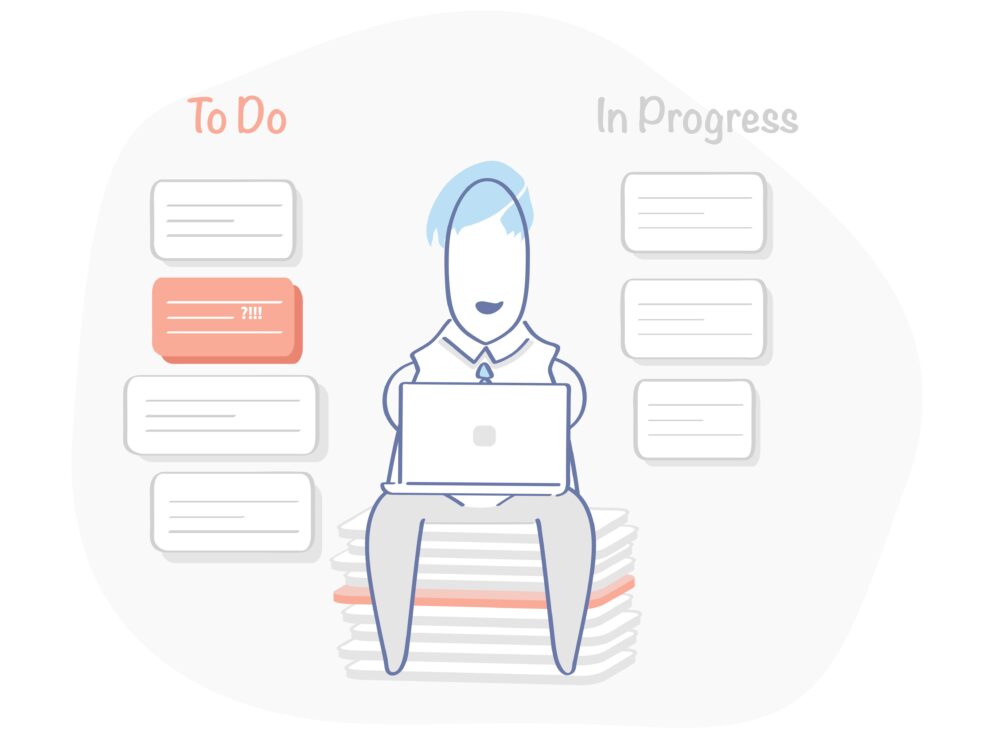お客様は神様?カスタマーファーストの実現に重要な3つのポイントと誤解しがちな注意点

様々な企業で「カスタマーファースト」は重視されています。しかし、実際にどのようなことをしたらカスタマーファーストを実現できるのか、具体案がわからない方も多いのではないでしょうか。本記事では、カスタマーファーストを実現させるために重要な3つのポイントや、注意点を紹介します。
カスタマーファーストとは
「カスタマーファースト」とは、日本語では「顧客第一主義」と言われます。特にサービス業において、顧客のことを考えて行動するための基本的な方針として使われることの多い言葉です。
カスタマーファーストはなぜ重要なのか
カスタマーファーストは、企業が顧客のことを考え抜き、本当に必要な商品やサービスを提供するために重要な考え方だと言われています。多種多様な商品やサービスが生まれる中、顧客のことを考えぬいたものが選ばれるようになっていることから、顧客に選ばれ続け、生き残るための戦略としてもカスタマーファーストの考え方は重要なのです。
カスタマーファーストの注意点
次に、カスタマーファーストを考えるときによく間違いがちな考え方と、注意点を紹介します。
「お客様は神様」ではない
カスタマーファーストというと、「お客様は神様」という言葉が思い浮かぶ方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、どのような顧客も神様のように扱うことは、本当の意味でカスタマーファーストとは言えません。
自分勝手な要求をして他の顧客の迷惑になったり、不利益を被ったりする顧客までを神様のように扱っていては、他の大多数の顧客の利益を無視するとになります。カスタマーファーストは、クレーマーや過大要求をする顧客に対しては、厳格な対応をすることも辞さない姿勢だと覚えておきましょう。
自社や社員を犠牲にすることではない
カスタマーファーストは「自社や社員を犠牲にして、お客様を優先させる」ということではありません。本当の意味でお客様のことを考えると、良いサービスを継続的に提供し続ける必要があります。そうするためには、自社の社員が気持ちよく働ける環境を整えることも必須だとわかるでしょう。
誰かを犠牲にして顧客を優先するのではなく、顧客のことを考えるために働きやすい環境を作ることもカスタマーファーストに大事なことです。
カスタマーファーストを実現する方法
最後にカスタマーファーストを実現する3つのポイントを紹介します。
全社員にカスタマーファーストの理念を共有する
カスタマーファーストを実現する1つ目のポイントは、「全社員にカスタマーファーストの理念を共有する」ことです。
顧客に直接対峙する部署だけでなく、全社員に「自分たちは顧客の幸せのために商品やサービスを提供している」と理念を浸透させることで、全社を上げて顧客のことを考え商品やサービスをつくることができます。また、理念が浸透することで、目先の目標のために働くのではなく、顧客のことを考えて理念を達成するには何をするべきか本質を考えて行動できるようになります。
CCOをはじめ、カスタマーファーストの実現の責任者をたてる
カスタマーファーストを実現する2つ目のポイントは、「カスタマーファーストについての責任者をたてる」ことです。
カスタマーファーストをふわっとした概念として持つのではなく、誰が責任を負うのか決めることでより現実的に取り組むことが可能です。
CCOというポジションを立てること自体が、社内外に対して、顧客を大切にする姿勢を強力に示すことができます。
カスタマーサティスファクションやカスタマーディライトなどの指標を利用しKPIを立てる
カスタマーファーストを実現する3つ目のポイントは、「指標を使ってKPIを立てる」ことです。
指標を作り、数字に表すことで、より具体的にカスタマーファーストのための施策を進められるようになります。
カスタマーファーストを考えるときによく使われる考え方は、カスタマーサティスファクション(顧客満足)や、カスタマーディライト(顧客感動)などです。これらの考え方で利用される指標を使うのもいいでしょう。
カスタマーファーストはCSチームが重要な鍵
カスタマーファーストを実現させるためには、直接顧客とコミュニケーションを取ることが多いカスタマーサポートチームが重要な鍵となります。
カスタマーサポートチームは、顧客対応だけで手一杯になっていることが多いでしょう。顧客対応をスムーズに進めるために、株式会社PR TIMESが運営する「Tayori」を利用することがおすすめです。
Tayoriでは、顧客からの問い合わせを一元管理することができ、チームで顧客の声を見える化できるため、対応漏れを無くし、、よりスピーディーに対応可能です。
また、よくある質問ページをWEB初心者でも構築ができ、カスタマーサポート担当が状況に応じて常に最新の状態にアップデート、公開ができるため、顧客にとっても有益な情報を問い合せせずに確認できるメリットもあります。
無料で利用できる機能も数多くあるため、まずは導入を検討してみてはいかがでしょうか。