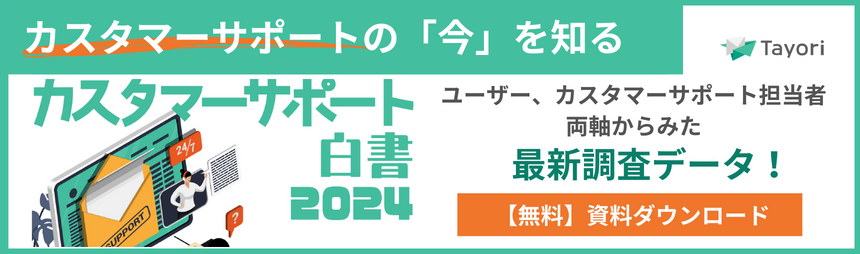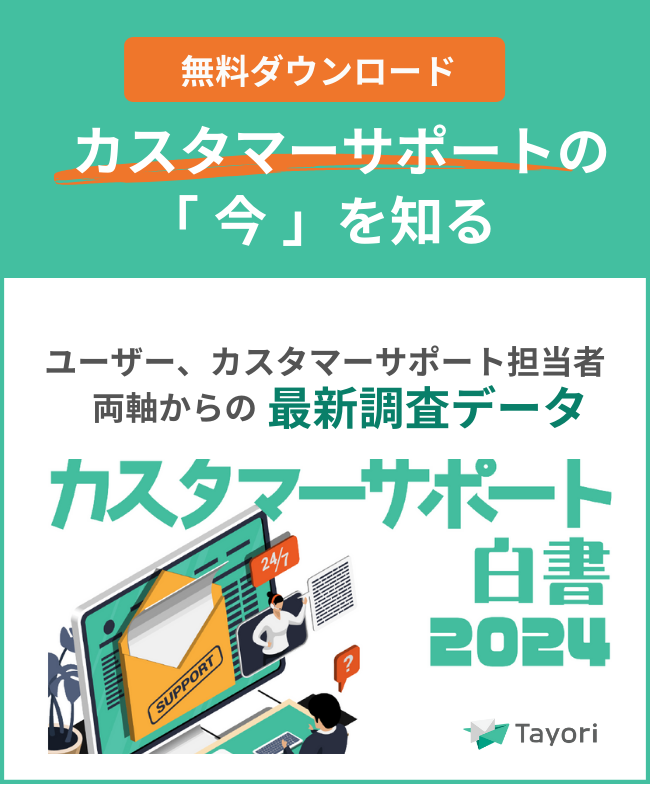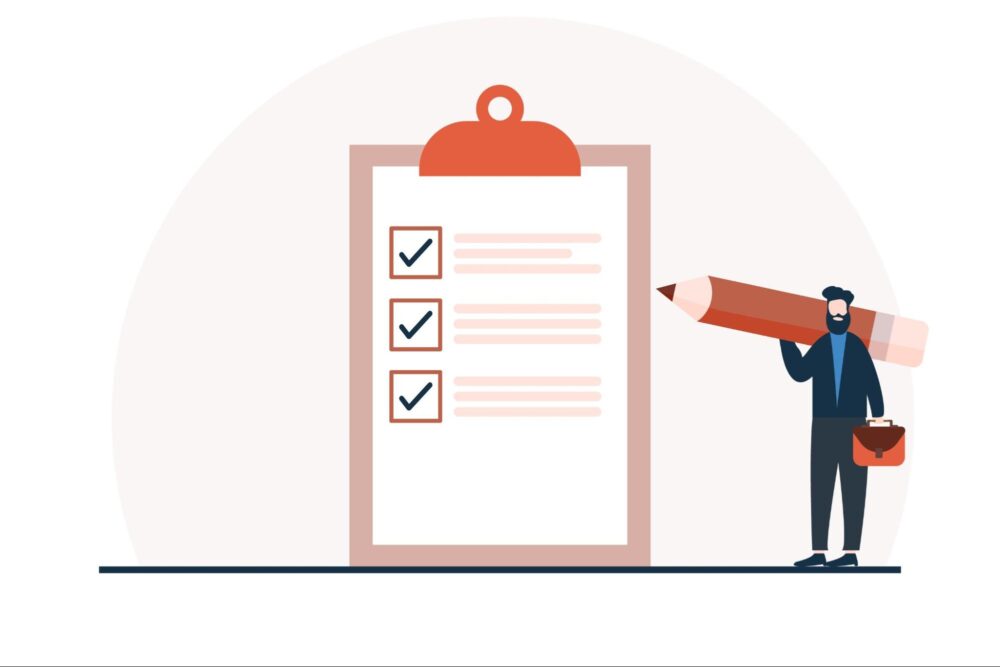労働災害における経験則のひとつである「ハインリッヒの法則」。ビジネスの文脈では、クレームを減らし、顧客満足度の向上に役立てる際にも使われる考え方です。
本記事では、ハインリッヒの法則について詳細に解説。関連するバードの法則やドミノ理論も紹介しながら、ビジネスへの活用術をお伝えします。
ハインリッヒの法則とは?
ハインリッヒの法則は、労働災害における法則の1つ。ビジネスにも活用できます。
さっそく意味や法則の例などを確認していきましょう。
ハインリッヒの法則の意味
ハインリッヒの法則は、「1件の重大事故が起こった際には、29件の軽微な事故、300件の事故寸前の危機的状況が背景にある」という考え方です。
「1:29:300」の比率から「1:29:300の法則」とも呼ばれます。
また、300件の事故寸前の危機的状況、いわゆる「ヒヤリハット」な状況があるという考え方から「ヒヤリハットの法則」とも呼ばれることもあります。
ハインリッヒの法則の根拠・背景
ハインリッヒの法則は、1929年に、アメリカのハーバード・ウィリアム・ハインリッヒ氏が提唱しました。
当時、ハインリッヒ氏はアメリカの損保会社に勤めており、5,000を超える労働調査を実施。統計を基に、導き出されたのがハインリッヒの法則です。
なお、ハインリッヒ氏は下記の基準を基に、事故の重大さを判断しています。
1件の重大事故:保険業者や行政に報告のあった事故
29件の軽微な事故:擦り傷や打撲などの軽傷を伴う事故
300件の危機的状況:怪我は伴わないが、一歩間違えれば怪我に繋がっていたトラブル・事故
ハインリッヒの法則の例
ハインリッヒの法則を、具体例を見ながらわかりやすく解説しましょう。
例えば、工場で腕の切断を余儀なくされるレベルの重大事故が、1件起こったとします。
事故をきっかけに詳しく調べてみると、身体の一部を切断したり骨折したりといった大きな事故はほかになかったものの、擦り傷や打撲などの軽傷を伴う事故が29件も発生したことがわかりました。
さらに調べると、怪我はなかったものの、怪我に繋がりかねないトラブルや事故の件数は、300件にも上りました。
1件の重大事故の背景には、結果的には重大事故にはならなかったものの、計329件もの「危険な状況」があったことがわかります。
当然、それほど多くの「危険な状況」があったのは、安全への配慮不足が原因です。
「油断大敵」といえばわかりやすいでしょうか。普段の心がけがしっかりしていないと、いずれは重大な事故が起こるということを示しています。
バードの法則とは?
ハインリッヒの法則と似た法則に、「バードの法則」があります。バードの法則では、「1:10:30:600」という比率が用いられます。
【バードの法則における比率】
1:重症を伴う重大事故
10:軽傷を伴う事故
30:物損のみの事故
600:怪我や物損寸前の危機的状況
ハインリッヒの法則に物損事故が加えられたものであり、重大事故と軽傷を伴う事故の比率も若干異なります。しかし、重大事故の背景には、配慮不足による危険な状況があるという考え方は変わりません。
なお、バードの法則はハインリッヒの法則がうまれた40年後、1969年にFrank E.Bird Jr.氏が提唱。297社の175万件もの事故報告の調査・統計に基づき提唱されました。
ドミノ理論とは?
ドミノ理論とは、ハインリッヒ氏が提唱した、重大事故を防ぐための理論。重大事故の原因を紐解き、軽微な事故や危機的状況の前段階から防ごうという考え方です。
1件の重大事故の背景には、329件もの事故・危機的状況があると唱えたハインリッヒ氏。
「重大事故には至らなかったものの、軽傷を伴うような事故はなぜ起こったのか」
↓
「普段は怪我をするまでには至らないちょっとしたトラブルが、たまたま今回は怪我に繋がったからだ」
↓
「では、トラブルが多いのはなぜか。よく観察してみると、安全への配慮が足りていないことがわかった」
と、倒れたドミノを元に戻すように、重大事故の原因を遡っていくのがドミノ理論です。根本的な原因を解決することで、重大事故や軽微な事故はもちろん、事故に繋がりかねないヒヤリハットを根本的になくそうとする考え方です。
ハインリッヒの法則をビジネスに活用しよう
ハインリッヒの法則の「事故」という言葉を「クレーム」や「欠陥」と置き換えれば、そのままビジネスに活用できます。
例えばある商品に、1つの重大な欠陥が隠れていたとしましょう。会社は商品の欠陥に気付くことなく、商品を出荷してしまいました。
商品には欠陥があるため、「すぐ壊れてしまった」「期待した効果が得られなかった」などのトラブルが起こります。1つの重大な欠陥によって、29件のクレームが発生するのです。
もちろん、クレームの裏には、より多くのサイレントクレームがあります。多くの顧客はクレームを出すことすらなく、不満を抱えたまま、2度と欠陥商品を出した会社を利用しなくなります。29件の裏には、300件のサイレントクレームが隠されており、会社は329件もの機会損失をしてしまうというわけです。
ちなみに、インターネットの発展した現代では、1件の欠陥に対して329件の機会損失では済まないでしょう。
商品やサービスの欠陥や不満は、SNSや口コミで世界中に広がり、3,000件以上の機会損失に繋がるともいわれています。
顧客の不満を把握するために、顧客の声と向き合うことが重要
ハインリッヒの法則をビジネスに役立てるためには、顧客の不満を把握することが大切です。顧客の不満を把握するためには、顧客の声と真摯に向き合わなければなりません。
商品やサービスに欠陥がないかを確認することは、もちろん大切です。しかし、人間はミスをするもの。「出荷やリリース前に欠陥に気付かない」というリスクは、ゼロにはできません。
しかし、普段から顧客の声と真摯に向き合っていれば、より早く欠陥に気付けます。不満をもった顧客にきちんとした対応をすることで、クレームが感動の声に変わったという事例は、耳にしたことがあるのではないでしょうか。
普段からアンケートや丁寧な問い合わせ対応を行い、内容をしっかりと管理することで、顧客満足度を高められます。
特にインターネットを使った「NPSアンケート」を活用すれば、顧客満足度だけでなく、顧客が企業やブランドに対する愛着・信頼を示す「顧客ロイヤリティ」も把握できます。
関連記事:NPS®とは?顧客満足度との違いや調査・計算方法まで解説
株式会社PR TIMESの運営するクラウド情報整理ツール「Tayori」を利用すると、アンケート機能を利用して、NPS®調査をすることが可能です。テンプレートを選べば本格的なアンケートが簡単に作成できます。

また、Tayoriを使うと、顧客からのお問い合わせを一元管理可能。CSVとしてダウンロードすることもできるため、顧客の声を知り、分析するときにも便利です。
これから、顧客についての理解を深めたい、問題になっているものを把握したいという方は、ぜひTayoriを活用してみてはいかがでしょうか。
また、Tayoriの導入によって業務効率アップができるか、チームでのご利用に最適な有料プラン(プロフェッショナルプラン)の無料トライアルもぜひ一度体験してみてください。